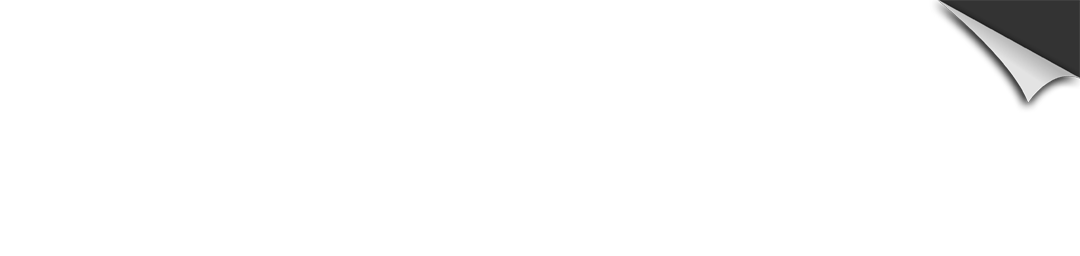初っ端から結論を書くようですが、「あなたにとって笑福亭鶴瓶とは如何様な存在か」と問われれば、もう「自信をなくす存在」と答えるしかない。
もちろんアタシ自身の喋りと鶴瓶の喋りと比較して、みたいなことではなくてね。
さて、現在のYabuniraの前身である「yabuniramiJAPAN」の第一期(2003~2007年)は途中から<笑い>ブログになっていました。
きっかけはダウンタウンのことを書いたからですが、いつしか現役で活動する、アタシが面白いと思う人を片っ端から論評しなければいけないみたいなムードになってね。んで、そんな空気を強く感じていたアタシは本当に片っ端から書き始めたのです。
そして2005年2月21日に「鶴瓶のこと」というエントリをアップした。ま、実際に、どんなことを書いたのかはお読みいただいた方が早い。ま、マクラと細かい補足箇所はカットしてますがほぼ全文です。
本日は鶴瓶のことですが、この人の場合、あんまりマジメに語ってもしょうがないのですよ。すべてが感覚の人であり、その感覚があまりにも無指向性なところから、すべてのおもしろさがそこから発信されていると思うのです。
でもそんなことはどうでもいいんです。それより鶴瓶のトークが楽しめない人のために、ひとつだけ<楽しむためのコツ>を伝授しましょう。
コツといっても実に簡単なもので、早い話が「何も考えずに聴く」というだけです。ボケーッと、半分馬鹿になって聴けばいいだけなんです。
これはベタベタな恋愛ドラマやドリフのコントといっしょで、つきつめて「何がおもしろいのか」なんて考えてたら絶対楽しめない。彼のトークは生粋のエンターテイメントなんです。つまり一過性の楽しさ。よくいえば後にひかない。悪くいえば何も残らない。でもそれが最大の利点というか。
なんとなく馬鹿にしてるみたいな書き方になりましたが、そんなことは全然なくて、それこそ「鶴瓶と花の女子大生」からずっとこの人のファンです。「突然ガバチョ!」などほぼ一回もかかさずみてたし、「ぬかるみの世界」は変なコミュニティみたいなのが成立してたんで入っていけなかったけど、「鶴瓶上岡パペポTV」はプロトタイプの「激突夜話」の頃からみてる。だから彼が東京でイマイチぱっとしない理由もわかるつもりだし、藤山寛美が松竹新喜劇で試みた「お好みリクエスト」をテレビで実現しようとして失敗した番組(番組名失念)も見てた。だからさんまが「おぼえてるよ」をギャグにしてやっと受け入れられだした時は本当にうれしかったですね。
なぜ大阪ほど東京じゃウケないかをアタシ流に解釈すれば、やっぱ東京の視聴者の方が、大阪の視聴者よりも<理由付け>をしたがると思うのです。「なんでおもしろいのか」っていうね。だから東京じゃさほどウケない。(こういうところが東京の笑いの弱点であり、長所でもあると思うんですけど)
でもそんな、東京の人に多い<鶴瓶が苦手な人>に「何も考えずに聴」けといわれても、求める笑いが違うんだからやっぱり無理なんでしょうね。そこで<楽しむためのコツ・斜め見編>を。
鶴瓶のトークの魅力は、上岡龍太郎が指摘した通り「昔の出来事でも、まるできのうのことのようにしゃべる」ことにあると思うのですが、出だしの部分の言葉で、それがいつ頃の出来事なのかがわかるです。
・「きのうもアレや」→一週間以内の出来事
・「こないだもアレや」→一年以内の出来事
・「前もアレや」→おとなになってからの出来事
これさえ理解していれば、よりマニアックに、よりいやらしく鶴瓶のトークが楽しめるはずです。
いやぁ、これは本当に酷いわ。今回は「どれだけ酷い内容だったか」を明示するのが目的だからいいんだけど、こんなのをたかがインターネットとはいえよくもまあ、恥ずかしげもなくエントリ出来たもんだわ。
これが単に「分析するために書いたけど、中途半端な形で終わってしまった」ってのならいいのですが、もう初っ端から「マジメに語ってもしょうがない(存在の人)」という投げやりなことを書いている。以降はどうでもいい駄文で誤魔化している。
とくに腹がたつし、情けなくなるのは「マジメに語ってもしょうがない」と書いた後にこんなことを書いている箇所です。
すべてが感覚の人であり、その感覚があまりにも無指向性なところから(以下略)
この頃はね、今と違って「読んでいただいてるみなさまへ」という気持ちが強かったはずなのに、まるで読み手を小馬鹿にしたような文章になってんだもん。
はっきりいって、こんな文章は「見くびり」の気持ちがないと絶対に書けないんです。「鶴瓶の笑いは<感覚>だ、とさえ書いておけばほとんどの人は納得するだろ」みたいなね。
鶴瓶の笑いが<感覚>の笑い?冗談言っちゃいけない。もし感覚でやってんのなら、あれだけムラがなく安定して長期間笑いを提供出来るわけがない。何しろ感覚なんて一番不安定なものだからね。
そこに気づかずに無邪気に<感覚>だ<無指向性>だと書いているのならまだ可愛げもあるけど、気づいていながら誤魔化してるっていう、その姿勢が情けないんです。
正直に言いましょう。今でも憶えているけど、構想ではね、もっとちゃんと「鶴瓶という芸人の面白さ」を自分なりの方法で分析するつもりでいたんです。
ところがやってみたら、まるで出来ない。つまりカンドコロみたいなものが何も掴めない。あれだけ鶴瓶の番組を見て、あれほど笑っていたのに、何がどう面白いのか説明せよ、となった途端、頭が真っ白になった。<感覚>ってのが違うのはわかってたけど、じゃあ何なんだ?となると、もう言葉が出てこない。
どうせまともなことが書けないのに引っ張るのは辛い、そう感じたアタシは誤魔化しでデッチ上げるしかなかったのです。
あまりにも悔しかったのでしょう。アタシはその後、何年にも渡りながら鶴瓶について書くことを止めていない。つまり何度も何度も「鶴瓶という芸人」の分析にチャレンジした。せっかくなんで一例を引用しておきます。(ただし文体は元の「だである調」から「ですます調」に変えてます)
笑福亭鶴瓶という存在はつくづく不思議です。テレビで局部を露出したり、大便したり、失禁したり、ほんらいなら危険極まりない芸人として認識されてしかるべきはずにね。
ところが「家族で乾杯」での、一般人の反応を見るまでもなく、非常に近しい、しかも関西弁でいうところの「ええ人」で通っている。
鶴瓶は番組の出演者やファンを連れだって旅行を行うのが好きで、大昔の「花の女子大生」や「ぬかるみの世界」からずっと、現在(現注・2009年)放送中の「ヤングタウン日曜日」でも、まだ、やっている。
ファンとふれ合おうという姿勢だ、という意見に異を唱える気はさらさらないんだけど、一歩間違えば、偽善的ととらえられてもおかしくないと思うわけで。
これまた大昔の「突然ガバチョ!」では、番組の最後に「スタジオに遊びに来てくれた人」(はっきりいえばただの番組観覧者)ひとりひとりに握手していたし、それにとどまらず、送迎バスまで見送るという徹底ぶりでした。
これを「偽善的行為」とみなすのはたやすい。もし、こういうことがやりたいとしても、何も番組の一部にすることはないんじゃないかという意見にも頷ける。
ところがです。ここまでストレートにやられると、偽善という感じがしないんですよ。
一時期さかんに「日本一感じのいいタレントを目指す」と吹聴していましたが、これがギャグになるのは、観客が鶴瓶のハチャメチャぶりを知っているからです。
しかも明石家さんまやナインティナインから「本当は悪い人」といわれることすら、そういわれることを許容することによって
表面はいい人
→裏では悪い人
→でも本当のホントは、やっぱりいい人
という公式がなりたってしまうというか。(2009年10月7日更新「偽善にならない男」※現注・このエントリはScribbleではオミット)
ま、だいたい、毎回毎回こんな感じっつーか、何度書いても結局一緒。分析はおろか「鶴瓶って面白いんだよ」ということすら読み手に伝えられてないような文章しか書けなかったんです。
少なくともこの頃までは、自分では<笑いの分析>にかんして、年季の入った、いわば得意技だと勝手に自負していました。ところが鶴瓶にはまったく歯が立たない。何だ、エラソーなことを言ってもぜんぜんダメじゃないか。
つまり「自信をなくす存在」とはそういうことなのです。
今「誰も味を真似できない」芸人といえば、間違いなく、さまぁ~ずでしょう。(中略)アタシもずいぶん長い間さまぁ~ずの番組をいろいろ見てますが、カンドコロがわかんないんですよ。 (中略)こういう人たちを理屈で分析しようとする方が無理で、いや分析できるのなら真似も出来ると思うんですよ。でも分析出来ないから真似も出来ない』(2015年8月16日更新「不思議な味わいのふたり」)
たしかにさまぁ~ずも分析が非常に難しい人たちです。しかし笑福亭鶴瓶はその上をいく。さまぁ~ずが副将なら鶴瓶は大将です。そのくらい難しい。
アタシは近年、何度も「笑いへの興味を失った」とか「笑いを分析するなんてカッコ悪いこと」みたいに書いてきました。
ただ、ひとつだけ心残りがあるとするなら、鶴瓶のことをちゃんと書けなかったことです。いや書く書かないではなく、自分の中でまるで分析が出来なかった。どうもそれが喉に小骨が引っかかったみたいに感じていた。
まったく興味のなかった人ならともかく、アタシはある意味明石家さんまやダウンタウンよりも鶴瓶の番組を選り好んで見てきたのです。下手したら今までで一番「積極的に見ようとした芸人」なのかもしれない。
そんな人を「分析は無理でした」で済ませておいていいのか。悔しくないのか、と言う気持ちが消えない。
ならば、やるだけやってみようと。
もちろん2005年に書いた酷いエントリへの罪滅ぼしの意味もある。もう誰も憶えちゃいないだろうけど、この際アタシひとりでもこだわろう、と。
正直言って自信はない。資料の精査を繰り返せばいつかはたどり着くってことではないんだし。どうしてもある種の閃きも必要になる。
ま、テキトーにお読みください。
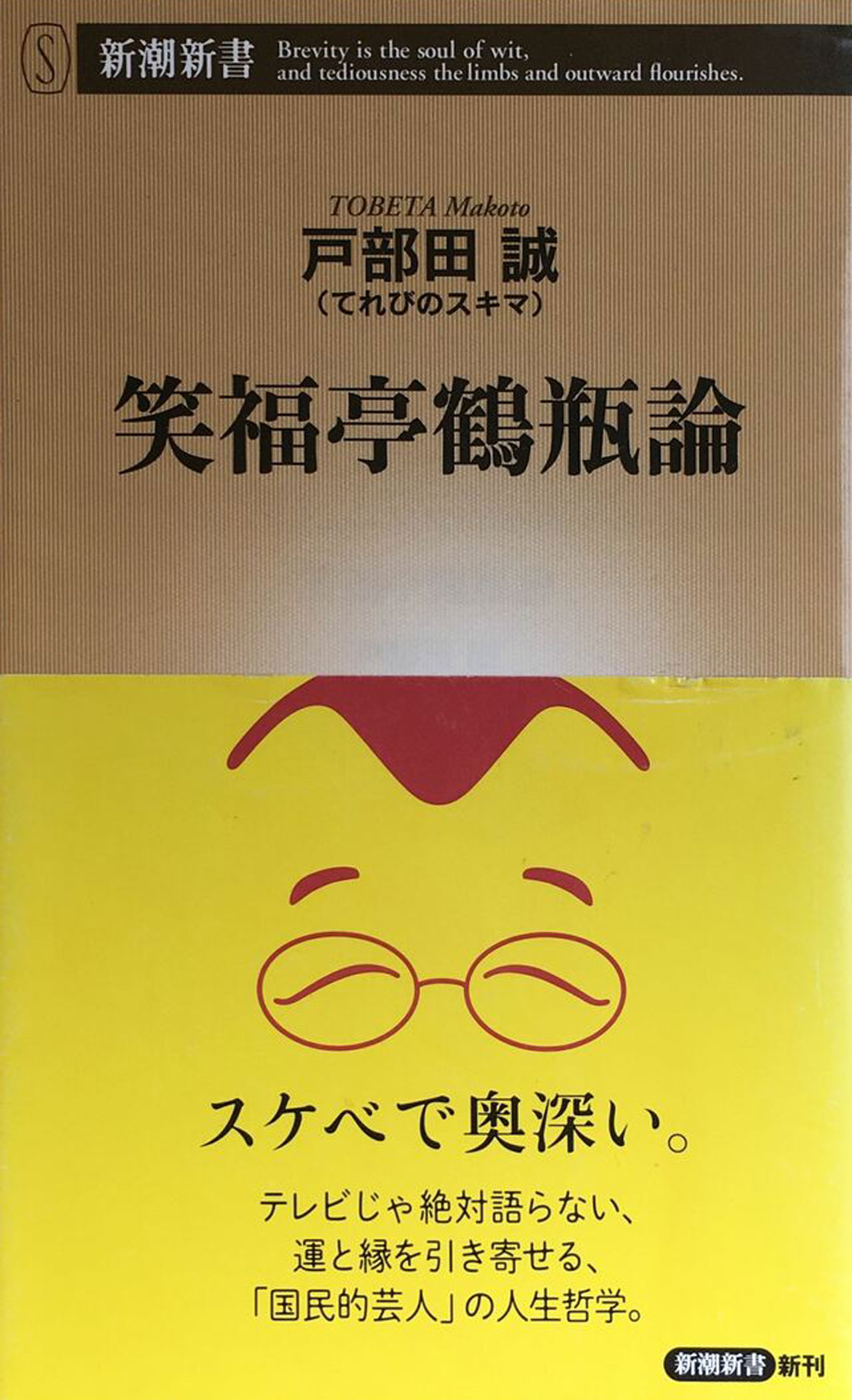 まず最初に、笑福亭鶴瓶という芸人の足跡や裏話を知りたいのであれば、これから書く駄文なぞは読まずに素直に戸部田誠・著「笑福亭鶴瓶論」(新潮新書)を読むことをオススメします。
まず最初に、笑福亭鶴瓶という芸人の足跡や裏話を知りたいのであれば、これから書く駄文なぞは読まずに素直に戸部田誠・著「笑福亭鶴瓶論」(新潮新書)を読むことをオススメします。
「笑福亭鶴瓶論」は本人への取材は一切しておらず、過去に本人の口から語られたこと、また周辺の人たちが鶴瓶について語ったことをまとめている。口さがない人は「この本独自の情報がないので価値がない」と言うのでしょうが(amazonのレビューでも実際あるし)、こと鶴瓶について語るなら本人への取材をしなかったことは正解だと思うわけで。
本の最初の方で、鶴瓶を分析するのはかくも難しい、ということにページが割かれていますが、これは前述の通り、アタシとまったく同意見です。
アタシと違うのは、著者は「スケベ」というワードから過去の言動を洗い直し、ジワリジワリ周りから固めていく作戦を取っている。
これはこれで悪くない。というかキチンとした論評として仕立て上げるならこの方法しか考えられない。下手に本人に取材してしまうと余計わからなくなるはずで、そういう意味でよく練られている好著と言えると思います。
アタシがやろうとしているのは「笑福亭鶴瓶論」とはまったく違います。
アチラは書籍、コチラはインターネットサイト。媒体が違うんだから違って当たり前なんだけど、周りから固めるといった七面倒なことは必要ない。ストレートに「何がオモロイのか」だけを語れば十分です。
これが「浅草」や「吉本」と言った、世間であまり知られてない話から論じるのならともかく、鶴瓶は十分すぎるほど世間に知られている。とくに関西の人なら「鶴瓶で一度も笑ったことがない」というような人を探す方が難しい。だから鶴瓶本人についての言及は必要ないんです。
アタシがやりたいのは「鶴瓶はこんな発想で笑いを作っている」とか「こんな生い立ち、人生が鶴瓶という芸人を形成した」みたいな話じゃないのです。
これはインターネットで発表する駄文だから許されることだと思いますが、これからやろうとしているのは「何故人々は、鶴瓶の話を聴いて笑い転げるのだろう」というね、あくまで受取手に主眼を置いて語りたいんですよ。
実は鶴瓶の芸には系譜みたいなものがまったくないのです。師匠である笑福亭松鶴と違うのは当然として、話芸の達人として知られた西条凡児や、憧れていたという横山ノックともまるで違う。

もしかしたら、弟子入りしたいとまで思ったという渥美清が一番近いのかもしれないけど、そもそも渥美清はテレビなどのメディアでほとんど話芸を披露していない。つまり渥美清を参考に話芸を練り上げた可能性は皆無です。
何でこんなことにこだわるのかというと、人間というのは「系譜のない芸」にものすごい不安を覚えるのです。歌舞伎、とか、落語、とか、ああこの人はあの系譜の中で育まれてきた人だ、と思うだけで安心出来る。芸の巧拙を問わずあたたかい眼差しでその芸人を見ることが出来るんです。
たしかに鶴瓶の出自は噺家かもしれないけど、どう見ても落語の系譜ではない。一見徹底的な無勝手流であり、受取手の心の拠り所みたいなものが何もない。むしろ受取手を突き放すやり方だとさえ言えるわけで。
「鶴瓶上岡パペポTV」において長年コンビを組んだ上岡龍太郎も無勝手流ぽいけど、出自も育んだ世界もはっきりしていた。「漫画トリオ」の一員として横山パンチの名前で顔が売れていたからです。すでに顔が売れていた状態だったから無勝手流を貫けたというのは確実にある。
あのダウンタウンでさえデビューしてしばらくは伝統の中にある漫才をやっていたし、明石家さんまがブレイクしたのは「喋り」ではなく形態模写という、これも伝統のあるスタイルだった。
ところが鶴瓶は違う。デビュー当時からすでに今のスタイルだった。
基本は鶴瓶噺であり、時たま狂ったように無茶苦茶に暴れ回る。かと思えば妙にしんみりした話に持っていきたがりもする。
この支離滅裂ぶりに一番手を焼いたのは、師匠の松鶴だったのではないか、という気がするのです。
松鶴の人生が支離滅裂だったことは有名ですが、半ば芸人の業として支離滅裂を演じていたというのはあったと思います。今はともかく、松鶴が頭角を現した時代においては、芸人が支離滅裂なのは賞賛にこそなれ誹謗にはならない。

鶴瓶は松鶴から落語を教えてもらっていない。通説では「コイツは落語という枠にはめるよりも好き勝手やらせた方が伸びる」という見識から落語を教えなかったと言われています。
が、どうもこれがアタシには胡散臭く感じる。何だか綺麗事すぎる、と。
アタシの見立てはこうです。
支離滅裂な狂人を松鶴は半分<素>で、半分<演技>でやっていた。そこに、まごうことなきホンモノの狂人が弟子として来た。駿河学、のちの鶴瓶です。
松鶴は鶴瓶と接すれば接するほど恐怖を感じたのではないか。こんなホンモノの狂人は自分の手に負えない、と。
「笑福亭鶴瓶論」では「鶴瓶はスケベである」という仮説からすべてを組み立てていってます。一方アタシは「鶴瓶は狂人である」ということから仮説を立てていきたい。狂人というフィルタを通せば、何故人々が不安を覚えやすい無勝手流にもかかわらず、これだけ長期間、老若男女に受け入れられてきたか、その鍵があると踏んだからで。
鶴瓶本人も散々「オレほど気軽に声をかけられる人間もおらへん」と言っているように、まァ親しみを持たれやすい芸人であるのは間違いありません。
ただ、アタシの場合はテレビ越しでしか知らないのですが、もし街で見かけたとしても鶴瓶ほど声をかけづらい人はいないなァと思うわけで。
何故、そんなふうに思うか、いや理由云々よりも何故アタシが笑福亭鶴瓶という<人間>にある種の恐怖心を抱くのか、その話はPage2へ続く。