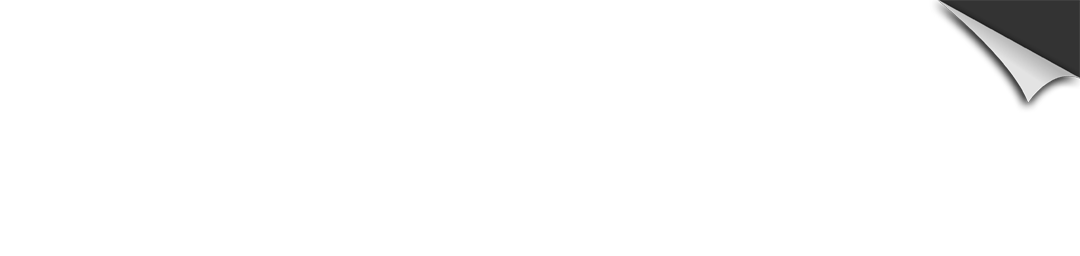まずアタシのフィクションにたいする考え方を書いておきます。
フィクションとひとくちに言いますが、フィクションにおいての登場人物はすべて、実在しない人ってことになる。もちろん実在の人物をモデルにしたり、実在の人物を実名のまま登場させるケースはありますが、そういう場合でさえ、まずその人物がどういう人物なのかを「手短に端的に描く」必要があります。
いわゆるキャラクターエピソードというヤツですが、これが非常に難しい。本来、登場人物の数だけキャラクターエピソードが必要なはずで、ダラダラやったら本筋が描けなくなるし、テキトーにやったらそもそも物語が成立しない。
ところがキャラクターエピソードをテキトーにやってるフィクションが実に多いんです。
アタシはね、キャラクターエピソードの出来がフィクションとしての出来を左右するとさえ思っている。というよりは、ストーリーの面白さとフィクションとしての出来不出来って実はあんまり関係ないんですよ。
面白いストーリーというのは「どこかで見たことがあるストーリー」である場合が多い。つまりこれが<王道>というヤツです。王道ストーリーは「人々が面白いと感じやすい」とすでに実証済みで、しかも先人たちによって練り込まれたものです。
もちろん王道から外れた、なのに面白いストーリーが作れればいいですよ。でもこれは不可能に近い。どれだけ天才と言われている人でも生涯一本か二本作ることが出来れば上出来です。それくらい難しい。
これでは、そりゃあ「商売なんて考えない。自分の作りたい作品を一本だけ作って、もう二度とフィクションは作らない」なんて人がいないとは言わないけど、少なくともプロではありません。
やはり、プロと言われるからには、ましてや映画のようなカネのかかるプロジェクトの場合は「コンスタントに高い打率を稼げる」能力が求められるわけです。
となると、王道ストーリーを利用しない手はない。もちろんノンアイディアで王道をなぞるだけでは「ただ無難なだけの新鮮味のない」ものにしかならないけど、王道を利用しながらストーリーとは別のところで新鮮味を出していく。こうしてクオリティを安定させるのがプロのフィクションの作り手です。
こうなるとストーリーというか大雑把なシノプシスで大きな差は出ない。となると如何に登場人物を魅力的に描けるか、が重要になってきます。
にもかかわらず、漫画なら絵、映画なら俳優の、いわばビジュアル頼みになってキャラクターエピソードの手を抜いたフィクションが多いのですよ。
 たしかに「手短に端的に」やるのが難しいのはわかるのですが、アタシが思うに黒澤明ほど上手い人はいないと思う。それは「七人の侍」においての、勘兵衛が浪人をオーディションするシーンを見るだけで十分すぎるほどわかるはずです。
たしかに「手短に端的に」やるのが難しいのはわかるのですが、アタシが思うに黒澤明ほど上手い人はいないと思う。それは「七人の侍」においての、勘兵衛が浪人をオーディションするシーンを見るだけで十分すぎるほどわかるはずです。
あそこは本当にすごい。結果仲間となる侍を手短ながらも「どんな性格か、どのような人生を歩んでここまで生きてきたか」が完璧にわかる。
実はもうひとつ、いわば「セカンドキャラクターエピソード」まで用意されているんだけど「七人の侍」の話ばかりになるから割愛します。
あと「生きる」も実に見事なもので、何と開巻すぐに、ナレーションベースで主人公の性格や今現在置かれている状況を説明するのです。
 まァいやこれは掟破りのようなもので、普通はナレーションで<補足>するのはいいけど<全部語らせてしまう>ってのは一番やっちゃいけないことなんです。
まァいやこれは掟破りのようなもので、普通はナレーションで<補足>するのはいいけど<全部語らせてしまう>ってのは一番やっちゃいけないことなんです。
でも「生きる」という映画自体がある意味特殊なフィクションで、何故なら「そもそもストーリーなんてないに等しい」のですよ実は。
あれは主人公のキャラクターエピソード自体が本編なのです。主人公がどんな人間なのかを描くことで映画として成り立っている。「手短に端的に」の正反対をやって、でも映画として抜群に面白いから驚異的なのです。
こうして見ていくと、黒澤明という人は、こと<物語る>ということにかんしては愚直というか実にシンプルで、ほとんどエゴを出さない。やるべきことをちゃんとやらなきゃ観客に伝わらないじゃねぇか、観客に伝わらないんじゃ、何のために映画という媒体を使う意味があるのか、みたいなものを感じるんです。
もう一度おさらいしますが、もともと黒澤明が志していたのは絵画です。絵画だって美術館に展示する場合などは観客はいるのですが、同時にとなるとせいぜい10人が関の山で、映画のように数百人単位が同時に同一空間で見るものではありません。
絵画ならば、もしかしたらわかりやすさよりもエゴの方が大事かもしれない。しかし映画で大切なのは「まず、大多数の人が容易に理解出来ること」ではないのか。
これも、P.C.L.に入社するまで映画に興味がなく、山本嘉次郎という娯楽映画の名手の元でイチから学んだからこその発想だと思う。
では黒澤明にはエゴがなかったのかというと、もちろんそんなことはない。ただし<物語る>以外のところでエゴを出した。
とくに元画家ということもあって絵作りにはものすごくこだわった。それはPage1で書いたように美術や衣装に異常なほどこだわる、という面でもあきらかです。
そしてもうひとつ、黒澤明と言えばとっくに総天然色、つまりはカラー映画ですね、の時代になってもモノクロ映画にこだわり続けたことです。
一般には「元画家だから色合いへのこだわりが強すぎて、しかし当時のフィルムの性能では自分の思う色が出せないからモノクロにした」と言われていますし、黒澤明自身もたびたびそのように語っていた。
でもアタシは、どうもこれは嘘くさいというか、いや嘘と言っちゃうと語弊があるけど、そもそも「カラー映画にするメリットよりもデメリットの方が大きい」と考えていたんじゃないかと思うんですよ。
ここでどうしても必要なので、黒澤明の師匠である山本嘉次郎のことを書きます。
もともと日活に所属していた山本嘉次郎が新興映画会社だったP.C.L.に呼ばれたのはエノケンこと榎本健一のたっての希望だったと言います。
 エノケンと山本嘉次郎の付き合いは古く、エノケンが京都でくすぶっていた頃、日活の京都撮影所でくすぶっていた山本嘉次郎と意気投合し「いずれ、一緒にモダニズムに溢れる音楽喜劇映画を作ろう」と約束した。そしてそれを憶えていたエノケンが「自分が主演の映画を撮るなら山本嘉次郎さんに撮って欲しい」とP.C.L.に頼み込んで日活から引き抜いてもらったのです。
エノケンと山本嘉次郎の付き合いは古く、エノケンが京都でくすぶっていた頃、日活の京都撮影所でくすぶっていた山本嘉次郎と意気投合し「いずれ、一緒にモダニズムに溢れる音楽喜劇映画を作ろう」と約束した。そしてそれを憶えていたエノケンが「自分が主演の映画を撮るなら山本嘉次郎さんに撮って欲しい」とP.C.L.に頼み込んで日活から引き抜いてもらったのです。
結果、山本嘉次郎のモダニズム志向はそのままP.C.L.のカラーになった。そんな山本嘉次郎から教えを請うた黒澤明がモダニズム志向が強いのは当たり前であり、黒澤明の作る作品は時代設定関係なく「スタイリッシュでクール」な作風になったのです。
こうした「スタイリッシュでクール」(この場合のクールとはカッコいい、オシャレという意味)な内容であれば、映像はどう考えてもモノクロの方が向いている。つまりカラーにする意味が限りなく薄いんです。
というか今は何も考えずにすべての映画がカラーで作られますが、絶対にモノクロに向いている内容とカラーが向いている内容ってのがあると思うのです。
結果的に黒澤明初のカラー作品は「どですかでん」になりましたが、これは時代がどうこうは一切関係なく、単純に内容を考えたらモノクロよりもカラーの方が相応しかったから、だけのような気がする。
「どですかでん」はある種のファンタジーを目指した作品です。ファンタジーならばカラー、と考えるのは自然すぎるくらい自然なのです。
そう言えば、結局実現しなかったとはいえ、黒澤明監督、三船敏郎主演で「西遊記」を作ろうとしていた、という話は有名です。
 具体的にいつごろそんな話があったのか、そしてどの程度具現化していたのかはわからないのですが(かなり後年になって黒澤明抜き、三船プロダクションとアメリカの映画会社合作で西遊記の映画化プロジェクトがあったらしいが、これも頓挫している)、もし、黒澤明が西遊記を撮ることになったとしたら、時期関係なしに間違いなくカラーで撮影していたと思う。
具体的にいつごろそんな話があったのか、そしてどの程度具現化していたのかはわからないのですが(かなり後年になって黒澤明抜き、三船プロダクションとアメリカの映画会社合作で西遊記の映画化プロジェクトがあったらしいが、これも頓挫している)、もし、黒澤明が西遊記を撮ることになったとしたら、時期関係なしに間違いなくカラーで撮影していたと思う。
黒澤明は山本嘉次郎監督、エノケン主演の「孫悟空」のチーフ助監督をつとめた経験もあるのですが(ただし当時黒澤明は同じ山本嘉次郎監督の「馬」の撮影にかかりっきりで、実はほとんど関与してないらしい)、こうしたファンタジー物も手掛けてみたい、そして自分ならこう撮る、みたいなものは確実にあったと思うんです。(余談だけどこれが結実したのが晩年の「夢」のような気がする)
この辺は黒澤明のプロデューサー気質なのかもしれないけど、映画というメディアへの向き不向き、モノクロもしくはカラーへの向き不向きということにたいして敏感だったのは間違いない。
 個人的にそれが狂い始めたのは「赤ひげ」からだったような気がするんです。
個人的にそれが狂い始めたのは「赤ひげ」からだったような気がするんです。
というか「赤ひげ」はもしかしたら撮ってる途中で「これは映画という媒体には向いてないんじゃないか」と気づいてしまって、その迷いがそれまでの黒澤明作品には必ずあった「ユーモア」と「開巻から巻末まで一気に走り抜ける感覚」が欠如してしまった原因のように思う。
アタシ的に言えば「赤ひげ」は「面白い失敗作」です。失敗作なのに面白いってのが変なのは承知していますが、以降の黒澤明作品も「面白い失敗作」か「面白くない失敗作」のどちらかになった気がする。たとえば「乱」は面白い失敗作で「まあだだよ」は面白くない失敗作、というふうに。
成功作(本当に成功作と言えるのは「用心棒」までに限られると思う)から「フィクションとして学ぶべきところが多い」のは当たり前として、実は失敗作からも学ぶべきことはあるんです。
失敗作というくらいだから失敗はしているんだけど、失敗がわかるということは「もし成功していたら、つまり黒澤明は本当はこんなふうにしたかったんじゃないか」と考えることこそ、フィクションを勉強する上で最高の教材になるのではないかと思うんです。
もし、1950年代後半の時期に「乱」や「影武者」が撮られていたら、どんなふうになっただろう。いったい何が足りなかったから失敗作なのかをね、ビジュアル一切抜きの<物語る>ことだけに注力して考えてみる。
もし可能であれば、自分と同じ物作りをする仲間とね、欠席裁判じゃないけど、徹底的に討論してみてもいい。
こんなことが可能なのって、それこそ黒澤明と手塚治虫くらいなんですよ。
アタシは藤子不二雄の大ファンだし、小津安二郎フリークは嫌いだけど小津安二郎作品は好ましいと思っている人間です。でも藤子不二雄や小津安二郎では、いくらディスカッションしてもフィクションの勉強にはならないと思う。というか結局オタク的知識の開陳合戦になるのがオチです。というかアタシだって藤子不二雄の話になるとあまりにも大枠を掴むのが難しいからか、つい細部をほじくり出したような話になってしまうし。
そこが手塚治虫や黒澤明は違う。とくに黒澤明の場合、たとえば「蜘蛛巣城」の撮影裏話とか別に興味ないもん。というかオタク的な興味を惹かない。「野良犬の闇市のシーンって、本多猪四郎が復員兵の格好でやってた」とか、聞いたところで「ふーん」としか思わないんです。
だから、皆無とは言わないけど、黒澤明作品<ファン>は山のようにいれど、黒澤明作品<フリーク>(マニア、でもいいけど)は、ファンの数を考えれば、つまり相対的に見ればメチャクチャ少ないと思う。
一般の人にとっての黒澤明作品は「見たらメチャクチャ面白いけど、完全なエンターテイメントになり切っているので、しばらくすると内容をスカッと忘れてしまう」という体のものなんじゃないか。
 内容は憶えてないけど「メチャクチャ面白かった」って印象だけが強烈に残っている。何故面白いんだろ、とか、あの場面は何が言いたかったんだろ、みたいな、いわば「思わせぶり」なところがないので、良くも悪くも引っかかりがないのです。
内容は憶えてないけど「メチャクチャ面白かった」って印象だけが強烈に残っている。何故面白いんだろ、とか、あの場面は何が言いたかったんだろ、みたいな、いわば「思わせぶり」なところがないので、良くも悪くも引っかかりがないのです。
先ほど書いた「蜘蛛巣城」の弓矢のシーンもね、よくよく考えればすごいことをやってんだけど、鑑賞中は内容に没頭しているから<裏側>が一切気にならない。
黒澤明は「野良犬は技巧に走りすぎてしまった」と自戒していましたが、テクニックなんかいらないってことじゃなくて「テクニックが観客に伝わるようでは、それは内容に入り込ませることが出来てないからではないか」と考えていたんじゃないかと。
中には失敗気味のものも混じっているとはいえ「酔いどれ天使」から「天国と地獄」までは「テクニックがどうとか、裏側がどうとか一切考えることなく、ひたすら内容に没頭出来る」作品群です。いわば特級のエンターテイメントだと言っていい。
だから考察もあまりされない。先程より「何か自分でモノをこしらえようと思っている人間ならば」黒澤明の作品から学ぶものは実に多いと書いているのですが、別にそうではない人間にとっては「ただ面白い映画を撮るだけの人」です。
そうであれば、せっかくこの世に黒澤明監督作品なんてとんでもなく素晴らしいエンターテイメントがあるんだから、見ないと損です。
アタシは下戸なので「酒を飲めないなんて人生損してる」とよく言われますが、酒を飲めないことよりも黒澤明監督作品を見ずにして死ぬ方がよほど人生を損しているような気がするのですがね。
| マジで「一番推しの黒澤映画は?」と聞かれたら本当に困る。 単純に好みだけで言えば「酔いどれ天使」になるのかなぁ。でも「用心棒」も捨てがたいし、「七人の侍」と「生きる」も外せないし。 うん、やっぱり決められん。 |
|---|
@Classic @山本嘉次郎 @エノケン @エノケン映画 #黒澤明 #映画 #時代劇 #映像 #藤子不二雄 カラー 全2ページ 小津安二郎 手塚治虫 撮影期間 @エノケンの千萬長者 キャラクターエピソード 王道 三船敏郎 ズレ 欠席裁判 面白い失敗作 #上岡龍太郎 #ビートたけし PostScript #パクリ @戦前 #1950年代 #2010年代 #アニメ・漫画 #オタク/マニア #嗜好品 #施設 #本 #東宝/P.C.L. #松竹 #物理メディア #神奈川 #音楽劇 画像アリ