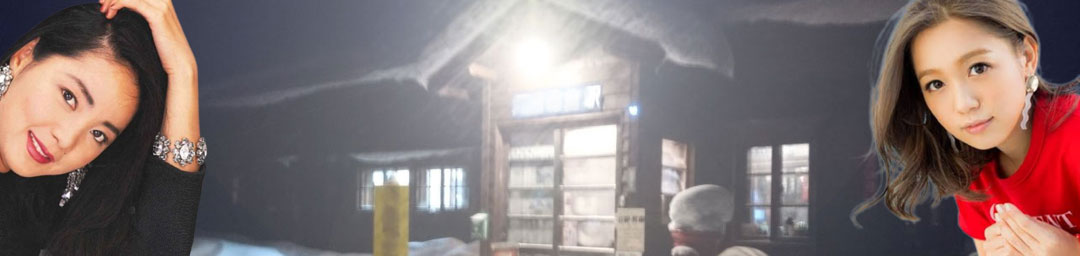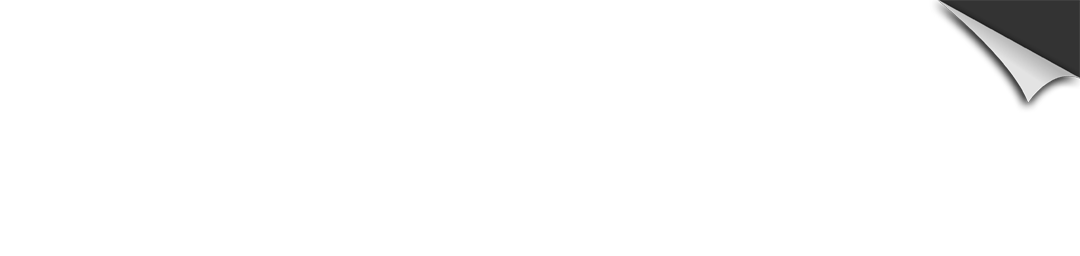ここからは1978年から1986年まで、オリコンチャートをずらずらっと見ていきます。あ、もちろん演歌だけね。
・1978年
なし
・1979年
1位 夢追い酒(渥美二郎)
3位 おもいで酒(小林幸子)
9位 みちづれ(牧村三枝子)
・1980年
なし
・1981年
2位 奥飛騨慕情(竜鉄也)
6位 大阪しぐれ(都はるみ)
・1982年
5位 北酒場(細川たかし)
・1983年
1位 さざんかの宿(大川栄策)
2位 矢切の渡し(細川たかし)
5位 氷雨(佳山明生)
・1984年
7位 娘よ(芦屋雁之助)
・1985年
なし
・1986年
なし
こうして見れば年によってかなりのバラツキがあります。
しかし逆に言えば「演歌だから全体のチャートに入るなんてあり得ない」というようなことはまったくなく、演歌だろうがムード歌謡だろうがアイドル歌謡であろうが、売れるものは売れる、とも言えるわけで。
ただし、1984年から、あきらかにムードが変わってくる。この年からムード歌謡や演歌といった(当時の)大人向け楽曲がランキングから目に見えて減っているのです。
大半はチェッカーズを含むアイドル歌謡か、もしくはテレビの主題歌(挿入歌)で、このあたりから「良い曲ならジャンル関係なく(正確には<流行歌>の範疇でさえあれば)売れる」という前提が崩れてきたとも言える。
それでも、まだまだ演歌愛好者はマイノリティレベルまでは減っていない。続いて1987年のチャートを。
・1987年
1位 命くれない(瀬川瑛子)
3位 雪國(吉幾三)
8位 無錫旅情(尾形大作)
9位 追憶(五木ひろし)
久しぶりに演歌が1位を奪回した上に計4曲もランクインしています。
が、この年が結果的に「演歌最後の輝きの年」になってしまった。
1988年以降、演歌はまったくベストテンに入らなくなり、ベスト30で言っても
・1988年
20位 命くれない(瀬川瑛子)
24位 祝い酒(坂本冬美)
27位 憂き世川(瀬川瑛子)
・1989年
26位 酒よ(吉幾三)
・1990年
15位 麦畑(オヨネーズ)
20位 恋唄綴り(堀内孝雄)
・1991年
なし
・1992年
なし
・1993年
なし
・1994年
なし
・1995年
なし
さすがに5年間、ベストテンどころかベスト30にさえ一曲もランクインしない、ということは、あきらかに演歌は売れなくなったと言える。
つまりは「1990年代以降、演歌はマイナージャンルに転落した」ということになるのですが、衰退の兆候はすでに1984年に表れており、1987年を「例外的当たり年」として見るなら、演歌の全盛期は1983年までとなる。
演歌だからと言って特別視されることなく、演歌が売れたのは1976年の「北の宿から」からで、その傾向が続いたのは1983年まで、となると、たった8年しかないのです。
たった8年!これは精査を始める前の事前予想よりも驚くほど短い。
グループサウンズの、甘めで4年、辛めで2年よりは長いけど、望郷ソングやわりとしつこく売れ続けたムード歌謡よりも<はるかに>短い、ということになってしまいます。
にもかかわらず、一定以上の年齢の人には「幼少より演歌を慣れ親しんでいた」というイメージがある。それもかなり強固なイメージが。
が「幼少より演歌を慣れ親しんでいた」のがどの年代かと言うと、実はアタシの年齢前後+-3歳ほどなのです。
アタシは1968年生まれですから、「女のみち」の時に4歳、「北の宿から」の時に8歳です。
アタシより上だと、すでに<好み>がはっきりした後に演歌が登場したことになるし、アタシより下では演歌が当たり前の時代を知らない。
ではアタシの世代、つまり1965年生まれから1971年生まれの世代で演歌が絶対的な存在かと言えば、まったく違うわけで。
21世紀に入ってからも、演歌全盛期に比べれば細々としたものではありますが、演歌歌手は次々とデビューしました。
一応名前を挙げておけば、氷川きよし、三山ひろし、福田こうへい、北山たけし、山内惠介、市川由紀乃、丘みどり、水森かおり、といったところでしょうか。

これらの歌手のファン層は、一般には「おばちゃん」と言われる。しかしこれはかなり忖度の入った言い方で、実際は「おばあちゃん」に相当する年齢の人たちです。
だいたいアタシの母親世代(ただしうちの母親は演歌には興味がない)、ということは、1940〜1954年生まれくらいではないかと推測出来ます。
アタシは世代論のようなものは信用してないのですが、そして甚だ個人的な感覚ではあるのですが、1955年生まれからは「世代が変わった」感覚が強い。
1955年生まれと言えば、明石家さんまです。そして翌1956年生まれと言えば、桑田佳祐であり、泉麻人です。
この人たちと演歌がどうしても結びつかない。もし「実は演歌が好きで」とか言われたら違和感の方が強い。
これがビートたけし(1947年生まれ)なら「実は演歌が好きで」と言われても、あんまり違和感がない。もちろんビートたけしにも演歌のイメージは皆無なんだけど、わりと素直に受け止められる。
それにしても、これはどういうことだろう、と思う。
アタシが推測した「演歌のターゲット=1940〜1954年生まれ」が正しいとするなら、「北の宿から」の時点ですでに大人に相当する年齢の人たち、ということになるわけです。
1970年代半ばは今とは時代が違うので、すでに大半の人は既婚者だったと思う。それでも新婚に近い頃であり、そんな頃に演歌に興味を持つか?とも思うのです。
少々勿体つけが過ぎました。
実は「演歌のターゲット=1940〜1954年生まれ」という条件は不十分なのです。
Page1にてアタシは「時代から(もっといえば高度経済成長から)取り残された人、ついていけない人、違和感を持つ人」をターゲットにしたのが望郷ソングだと書きました。
この感覚は高度経済成長が終わってからも長く続くことになった。とくに<田舎>と言われる地域は高度経済成長が始まっても、バブルの時代になっても、さほど街が発展するわけでもなく、あいも変わらずの田園風景や昭和30年代的商店が残存した。
1980年代半ば以降、時代は変わった。音楽のメインターゲットは若者、そして都会に住む者に絞られた。またしても田舎に住む、しかももう若くない1940〜54年生まれの人たちは再び「置いてけぼり」になった。
この頃すでに望郷ソングはほぼ消滅していましたが、その代わり、演歌が望郷ソングとムード歌謡のファン層をそっくりそのまま引き継いでいた。
つまりはこういうことです。演歌を幼少の頃から慣れ親しんでいたかどうかと演歌愛好者になるかどうかとはほとんど関係がない。
それよりも、時代の変化についていけない、もしくはついていこうにも実感として時代を感じ取ることが出来ない<田舎>に在住している、そのことの方が重要なのです。
こうした、ある種の<時代からの、もしくは文化からの疎外感>こそが演歌には必要だった。そしてインターネット全盛になって時代への疎外感、文化からの疎外感を感じにくい時代になった今、演歌がよりマイナージャンルになるというのは当然なのです。
いや、もっとはっきり言えば、現今の演歌は「疎外感を持つ者」の受け皿になっていない。
貧富の差がどんどん激しくなると言われる令和という時代、ネットで暴言を吐いているような人たちこそ、本来はターゲットにするべきなのです。
こんなことを言えば笑われるかもしれませんが、今の時代、演歌に相当するのは「なろう小説」なのです。
「置き去りにされた<心>」を癒やしてくれる、カタルシスを与えてくれるのは演歌ではなく一部のアニメや「なろう小説」である、と言った方がわかりやすいか。
一部には「なろう小説」を莫迦にする風潮がありますが、ちょうど演歌がマイナージャンルに転落する前後、演歌をものすごく莫迦にする風潮もありました。
とくに当時<新しい>と目されているニューミュージックやロックのアーティストあたりから、つまりは<プロ>からそういう声が挙がった。そしてそれを自身のラジオを通じて私見を撒き散らしてしまった。
考えてみれば、彼らは年代的には演歌のメインターゲットである1940〜54年生まれの人が多かったのです。そしてその中には当然田舎出身の人たちもかなりいた。
だから莫迦にした、というのは結果であり、元は私怨というか近親憎悪に近い。そして心のどこかには「実は演歌はそれほど憎むべきものでも莫迦にすべきものでもない。しかし、そう言わなければ自分たちが音楽をやっている存在価値がなくなる」という感覚だったのではないか、と穿ってしまうのです。
ただこれは失敗だったとつくづく思う。私怨でとどまっているうちはいいけど、それを発信することで「演歌=莫迦にすべきもの」、「演歌を聴く者=莫迦にされるべき人たち」という感覚を植え付けられた人がずいぶんいたと思うからです。
彼らからしても、実は演歌を叩き潰しても何のメリットもないのです。
演歌という<置いてけぼり>な人たちを対象にしたジャンルがあるからこそ、自分たちがやってる最先端の音楽が輝く、というのがわかってなさすぎた。いくら演歌を叩き潰しても、では演歌愛好者が彼らの音楽を聴くようになるかというと、ならない。なるわけがない。ただ音楽を聴く対象を減らしただけです。
それに気づいたのか、最近はむしろ、演歌を、そして演歌歌手を正当に評価しようという動きさえ出てきた。もちろん演歌がマイナージャンルになってしまったからだろうけど、最初からこの路線で行けば良かったのに、とつくづく思うわけで。
でも正直、もう遅い。彼らが発信した「演歌=莫迦にすべきもの」というイメージは意外としぶとかった。そしてその間に演歌にとって変わったのは「置き去りにされた心」を癒やしてくれる、カタルシスを与えてくれるのは、音楽とまったく関係ないジャンルが浮上して、演歌が入る隙間がなくなってしまったのです。
新しいファン層が付かない状況がある以上、演歌の寿命はどれだけ長く見積もってもあと20年もない。
いや、現今のファンのボリューム層である「忖度の入ったおばちゃん=おばあちゃん」がコンサートに行ける健康状態まで考慮するなら2030年頃には終焉を迎えることになってしまう。
たしかに演歌の歴史はイビツなものだった。
まず演歌という名称自体がいわば借り物だし、大ヒットした最初の曲がパロディという類のない始まり方だった。
愛好者は一部の年齢層に限られ、また居住地も限られ、淡谷のり子や一部のミュージシャンからは批判にさらされ、莫迦にもされた。
演歌の全盛期はたった8年しかないのに「演歌=莫迦にすべきもの」という風潮は20年以上に渡って残存した。
この悲劇性こそが、実は演歌そのものかもしれないけど、そんなことを「演歌に相応しい最期」と片付けていいのだろうか、とも思う。
ここまでアタシはあえてカラオケというものをオミットして書いてきました。
ただ演歌においてカラオケの果たす役割は大きい。何故なら演歌とはカラオケにおいて「上達を実感しやすい」音楽なのです。
これは非常に珍しいジャンルで、現今、演歌以上にカラオケで上達が実感しやすいジャンルは存在しないと思っている。
音楽というものは不思議なもので、受け取り手が「その楽曲を聴くだけで完結してしまう」ものと、もうひとつ、そこから広がって「自分で歌ってみたい、演奏してみたい」と思わせるタイプのものも存在する。(さらにもうひとつ、踊りたい、と思わせる、いわゆるダンスミュージックもあるんだけどそれは割愛する)
もちろん、一番気軽な「歌ってみたい」は鼻歌ですが、次の段としてカラオケやニコニコ動画における「歌ってみた(=歌い手)」なんかもあるけど、やっぱね、カバーされてる楽曲には「歌ってみたいと思わせる<何か>」があると思うんです。
 話は逸れますが、小室哲哉がいわゆる小室サウンドを作ろうと思ったきっかけとして「ディスコで踊った後でカラオケに流れ込んでも歌う歌がない」というようなことを語っていたことがあります。
話は逸れますが、小室哲哉がいわゆる小室サウンドを作ろうと思ったきっかけとして「ディスコで踊った後でカラオケに流れ込んでも歌う歌がない」というようなことを語っていたことがあります。
たしかに、ディスコでユーロビート系の音楽で踊っていた若い人たちが、カラオケに行ったからといって歌謡曲や演歌を歌うのは何か違う。
そこにマーケットが空いてると見抜いた、そして点数が出るカラオケが登場したことまで活かして「ひとつの楽曲内にあえて歌いこなすのが難しいポイントを入れる」、つまりカラオケにゲームにチャレンジするような要素まで付加したのは小室哲哉の商魂たる故でしょうが、言い方を変えればそれまで「嫌々」「しかたなく」カラオケで演歌を歌っていた層が絶滅してしまったわけで。
では今後、演歌がどうなっていくのか、そうしたあくまでアタシ個人の予想をPage4で書いていきます。
@Classic #複眼単眼 #音楽 #1970年代 @戦前 演説歌 古賀政男 藤山一郎 クルーナー唱法 美空ひばり ムード歌謡 望郷ソング 三橋美智也 女のみち ぴんからトリオ なみだの操 殿さまキングス 昭和枯れすゝき さくらと一郎 都はるみ パロディ 石川さゆり 忖度 氷川きよし 小室哲哉 テレサ・テン ミッヂ・ウィリアムス @川畑文子 江利チエミ 西野カナ 2023年11月28日大幅改稿 全4ページ #泉麻人 #明石家さんま #ビートたけし #漫才 PostScript #兵庫 #マジョリティ/マイノリティ #1950年代 #1960年代 #1980年代 #1990年代 #2020年代 #YouTube #アイドル #ラジオ #嗜好品 #大正以前 #大阪 #戦後 #施設 #映画 #東京 #松竹 #物理メディア #音楽劇 画像アリ 動画アリ