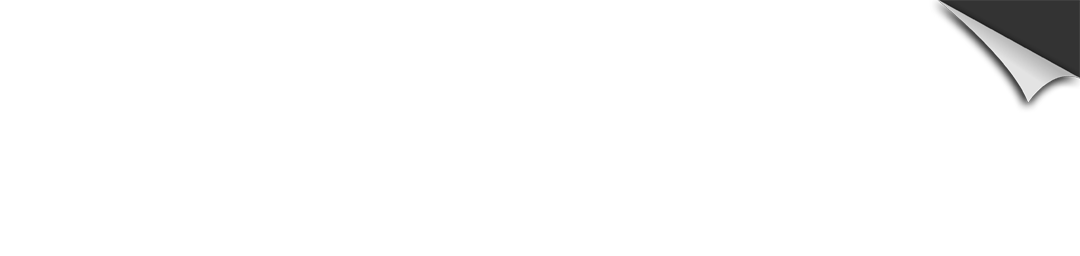♪ ン道中双六 振り出た賽にィ
江戸をたァびィだァつゥうッ ひざァくゥりィいげ~
 1939年制作「エノケンの弥次喜多」のオープニング曲で始まりました今回の「人形町道行」ですが、まずは通称・弥次喜多、つまりは「東海道中膝栗毛」の話から始めたいと思います。ま、人形町と関係ないっちゃ関係のない話だけど、人形町を語るとなるとこうした江戸末期の創作物のことを語っておくのも悪くないんじゃないかと。
1939年制作「エノケンの弥次喜多」のオープニング曲で始まりました今回の「人形町道行」ですが、まずは通称・弥次喜多、つまりは「東海道中膝栗毛」の話から始めたいと思います。ま、人形町と関係ないっちゃ関係のない話だけど、人形町を語るとなるとこうした江戸末期の創作物のことを語っておくのも悪くないんじゃないかと。
正直、アタシはとてもじゃないけど、古今の、世界中の創作物語を諳んじているわけではありません。だからもしかしたら先行例はあるのかもしれないけど、「東海道中膝栗毛」はおそらく世界初の「道中モノにして滑稽モノにしてバディモノ」です。
道中モノ、つまりはロードムービーのことで(映画じゃないからムービーってのも変だけど)、しかも滑稽モノ、まァ、喜劇、コメディですよね。
あくまで<笑い>という文化に根を生やしながら、物語の軸はロードムービー、要するに「物語の舞台が一幕毎にどんどん変化する」という体裁を取っています。
バディモノってのはもうそのまんま、バディ=相棒ってことですから、ふたりひと組の主人公ということです。
ここまで書けば、江戸時代に書かれたこの物語が見事なまでに「日本人が好きな要素が全部詰まっている」ってのがご理解いただけると思います。
例えば「男はつらいよ」など、完全なバディモノでこそないものの、道中でのてんやわんやを描いた喜劇です。
つまり、江戸末期の時点で、普遍的な「日本人が好む」世界観を描き出したってことになるんだから、十返舎一九の名声はもっとあっていいと思うんですがね。
もちろん「東海道中膝栗毛」は江戸当時から人気があったのですが、なんだかんだ、昭和のはじめまで、つまり戦前期までは「東海道中膝栗毛=弥次喜多」は絶大な人気があった。
さすがに昭和期に江戸期に書かれた原書が広く読まれたわけではない。では当時、どのような形で弥次喜多が親しまれたかというと「芝居」、つまり劇場で鑑賞する演目として親しまれていたのです。
とくに喜劇の劇団は夏になると必ずといっていいほど弥次喜多を演目に加えた。当代の人気喜劇劇団だったエノケン一座もロッパ一座も、やはり弥次喜多は<定番>でした。
もちろん話としてもキャラクターとしても弥次喜多は親しまれていた。観客には馴染みなんだから安心して演目に加えられるってのはあったんだけど、夏になるとってのが面白い。
当時の劇場は、もちろん劇場のランクによってもいろいろあったんだけど、大抵の劇場にはクーラーなんて気の利いたものはなかった。観客は暑くて狭っ苦しい中で芝居を見なきゃいけない。
だったらせめて、舞台上だけでも涼しげな扮装を、という配慮もあって、見た目如何にも涼しげな装いの弥次喜多が選ばれていたらしい。
ところが戦後になって、劇場がクーラー完備が当たり前になってくると、こうした配慮は必要なくなる。ということもあって戦後は弥次喜多は<定番>から外れたと。
もう一度戦前期に話を戻しますが、エノケンは文頭に書いたように「エノケンの弥次喜多」というタイトルで弥次喜多モノを映画化しているし、古川ロッパも1936年に「歌ふ弥次喜多」のタイトルで映画化しています。
 弥次喜多モノが面白いのはフィクショナルなっつーかファンタジー要素が強くなる赤坂並木の景で、何しろここは狐に化かされるっていう設定になっている。
弥次喜多モノが面白いのはフィクショナルなっつーかファンタジー要素が強くなる赤坂並木の景で、何しろここは狐に化かされるっていう設定になっている。
「エノケンの弥次喜多」はわりあいあっさりした描写ですが、「歌ふ弥次喜多」は一大レビュウになっており、戦前期のレビュウの一端が垣間見られます。
というふうに、たしかに弥次喜多の舞台設定は江戸時代なのですが、ファンタジーとして現代劇を入れ込むことも可能なのが面白い。
これは根拠が薄いのでアレですが、この赤坂並木の景を大幅に膨らませたのが「狸御殿」シリーズではないかと睨んでいます。
さて、この辺で本題に戻ります。
あ、その前にひとつだけ。「東海道中膝栗毛」の<膝栗毛>とは、要は馬(栗毛)には乗らずに己の膝を使って移動する、つまり徒歩という意味です。
だから「東海道中膝栗毛」ってのは江戸から東海道を徒歩で移動するって意味なのですが、今回のエントリはさすがにそこまではしない。というかそれでは人形町絡みのエントリにはならないし。
今回<膝栗毛>するのは、東京駅から人形町まで、という実に短い距離です。
ま、短いといっても30分ちかくかかるわけで、普通は地下鉄なりを使います。江戸時代ならともかく現代人は徒歩移動なんてしない。
しかし何のことか、かつてアタシはこの距離を、ほぼ2週間に一回の割合で<膝栗毛>していたのです。
あれはアタシが人形町に在住していた2002年から2003年のことです。当時アタシは、今ならばブラックと認定されてもおかしくないくらいの長時間労働を強いられており、家に帰れたとしても終電間際だった。
勤務地は新宿だったのですが、地下鉄に間に合わないとなると山手線で東京駅まで行って、人形町までは徒歩、というルートしかない。仕事を終えてから30分も徒歩移動ってのはムチャクチャなんだけど、もうそうするしかなかったっていうかね。タクシーなんて使わせてくれなかったしさ。
じゃあ、それが苦痛だったのか、というと、これがそうでもないんです。むしろ真夜中に東京駅から人形町まで徒歩でトボトボ帰るってのは、楽しみでさえあったんです。
実際、終電云々関係なく、アタシは何度も東京駅←→人形町を<膝栗毛>している。真夜中だろうが真っ昼間だろうが。何故なら歩いているだけで幸せな気分になれたから、というかね。
では具体的にどんなルートを通ったのかですが。
まずは甚だ簡単ではありますが、東京駅から人形町までを含んだ自家製の地図をご覧いただきたい。

こうして見ると、ざっくり「小舟町ルート」と「茅場町ルート」があるってのがわかってもらえると思います。
茅場町ルートは他に分けようもないんだけど、小舟町ルートは「永代通りルート」と「八重洲通りルート」に分かれる。つまりまず東に向かうか北へ向かうかに分かれるわけです。
ま、小舟町ルートにはさらに「日本橋経由ルート」と「江戸橋経由ルート」ってのもあるんだけどね。
たぶん個人的に一番使ったのは「小舟町(永代通り・日本橋経由)ルート」だったと思う。少なくとも人形町に滞在していた頃は。
ただ「自分がよく使ったルート」だけを書いていっても面白くないので、それぞれのルートを<膝栗毛>したら、みたいな感じでやってみたいと思います。
・・・と、ここまでが長い長い前フリ。長すぎるな。
どのルートを使うにしろ、始発っていうか始点は東京駅の八重洲口になります。日本橋口?知らん知らん!ワシャ、そんな出入り口は知らんぞ!!
気を取り直して、まずは小舟町ルート(の永代通りルート)からの説明です。ざっくり書けば、八重洲口を降りて外堀通りを北に向かい、永代通りを東進して中央通りを左折、日本橋を渡りすぐに右折、というルートです。
なにはともあれ、永代通りの入口(じゃないけど)である呉服橋交差点まで行かなくてはならない。つまり、八重洲口から大丸を左手に見ながら外堀通りを北進します。
アタシが人形町に在住していた2002~2003年当時、テンション爆アゲポイントが呉服橋交差点にあったのです。
とその前に、橋もないのに呉服<橋>とはこれ如何に、の説明から済ませてしまいますが、地図を見ていただければわかるように、東京駅から皇居、つまりかつての江戸城はほんのわずかの距離です。
明治時代までこの一帯には外濠があり、今の呉服橋交差点のところには呉服橋門が設置されていました。
が、城がなくなったことで外濠は文字通り埋められ「呉服橋」や「外堀通り」といった名前だけが残った、とこういうことです。
 で、ですね、1960年代の東宝映画を愛するアタシにとって呉服橋交差点と言えば「かつて大和証券本社ビルがあった場所」なのです。
で、ですね、1960年代の東宝映画を愛するアタシにとって呉服橋交差点と言えば「かつて大和証券本社ビルがあった場所」なのです。
アタシが人形町に在住していた頃まではまだ往時に近い姿をとどめており、いつ植木等が飛び出してきてもおかしくないくらい、守衛が沢村いき雄でないのが不自然なほどの外観を残していました。
 ここまで書けばわかる人はわかるでしょうが、主人公が勤めるオフィスビルのロケ地はたいてい<ここ>で(ま、外観だけだけど)、看板だけをすげ替えて、時には太平洋酒、時には明音楽器、とどの作品も<同じ>だったんです。
ここまで書けばわかる人はわかるでしょうが、主人公が勤めるオフィスビルのロケ地はたいてい<ここ>で(ま、外観だけだけど)、看板だけをすげ替えて、時には太平洋酒、時には明音楽器、とどの作品も<同じ>だったんです。
だからもう、このビルを見るだけでテンションが上がった。植木等になった気になってね、真夜中にこれから30分もかけて人形町まで歩いてかえらなきゃいけないのに「よーし、やるぞ!」とテンションが上がったのです。
残念ながら大和証券本社ビルはその後取り壊されましたが、あれは東宝映画ファンとしては残しておいて欲しかったなぁ。
続いて八重洲通りのルートを。どっちにしろ中央通りを左折するんだから先に済ませておこうと。
でも残念ながら、中央通りにぶつかるまで八重洲通りには何もない。駐車場覗いてもしょうがないし。
でも中央通りに出て以降、永代通りと交差するまでには髙島屋と丸善があるんだからこっちのルートも強い。
 髙島屋は一応「日本橋店」って名称だけど、「日本橋にある」ってことにするには微妙なのですが、それでも文句なしに「日本橋にある」と言える三越が味も素っ気もないのに比べると重厚感があって実に素晴らしい外観です。
髙島屋は一応「日本橋店」って名称だけど、「日本橋にある」ってことにするには微妙なのですが、それでも文句なしに「日本橋にある」と言える三越が味も素っ気もないのに比べると重厚感があって実に素晴らしい外観です。
大阪の梅田にある阪急百貨店が建て変わっちゃった今、本当に重厚感も歴史もある百貨店となると、もうここしかない。
 もうひとつの丸善もよく行ったなぁ。ま、アタシは英語が弱いので原書を漁るなんてことはないのですが、それでも実に堅実な品揃えで、外堀通りをやや南に行った八重洲ブックセンターよりも個人的には好ましい。
もうひとつの丸善もよく行ったなぁ。ま、アタシは英語が弱いので原書を漁るなんてことはないのですが、それでも実に堅実な品揃えで、外堀通りをやや南に行った八重洲ブックセンターよりも個人的には好ましい。
再びルートに戻ります。
 中央通りと永代通りが交わる日本橋交差点の北東辻には今はコレド日本橋という高級ショッピングモールがあります。
中央通りと永代通りが交わる日本橋交差点の北東辻には今はコレド日本橋という高級ショッピングモールがあります。
しかし戦前モダニズムを愛するアタシとしては、やはりここは「かつて白木屋本店があった場所」としたい。あ、白木屋と言っても居酒屋じゃないよ。かつて存在した百貨店です。
白木屋と言って一番に連想されるのはやはり「ズロース事件」でしょう。ズロースってのは、現今のパンティのことだと思っていただければいい。
1932年12月16日、クリスマスツリーの飾り付けの豆球から引火した炎は百貨店全体を火で包み、死者13人、傷者67人という大惨事になりました。
この火災にはとある伝説があって「火事の見物人に局部を見られるのを恥ずかしがった女性が着物の裾を抑えるため、思わず命綱を手放し転落して多数の女性が命を落とした」という。
現代でも着物の着用時には下着を着けないのがマナーと言われていますが、下着を着ける習慣のなかった日本人が大多数だった、というのは本当で、しかして「局部を見られるのが嫌で」「命を落とす」なんてあり得るのか、ですが、井上章一著「パンツが見える。羞恥心の現代史」にその答えがありますので是非御一読をば。
しかし白木屋はこの大惨事を乗り越え見事に復旧することになります。そして、少なくともわずか1年後にはほとんど火災の面影がないほどにまでなりおおせていたのです。
って、何でそんなことがわかるんだ?と思われるかもしれませんが、1934年1月公開のP.C.L.映画「只野凡児・人生勉強」にて白木屋が大々的にロケされているからです。
当時のP.C.L.はまだ東宝資本になる前で、映画製作資金の捻出に苦労していました。そこで半分PR映画にすることで、つまりはスポンサーを付けることで制作費用を調達していた。だからP.C.L.第1作「音楽喜劇・ほろよひ人生」は大日本麦酒(現在のアサヒビールとサッポロビールの前身)がスポンサーなので大々的にビールを飲むシーンが出てきますし、第2作「純情の都」は明治製菓がスポンサーなので、主人公のひとりが明治製菓の図案家(今で言えばグラフィックデザイナー)という設定になっている。
んで「只野凡児・人生勉強」は白木屋がスポンサー、ということは当然、白木屋で買い物をするシーンが出てくるという寸法なのです。

こうやって見ていただければお判りいただけますように、すでにエスカレーターもあるし、従業員が着物姿という以外はそんなに現代の百貨店と変わりがない。当時の文化水準の高さが十分にうかがえます。
てなわけで、Page2に続く。