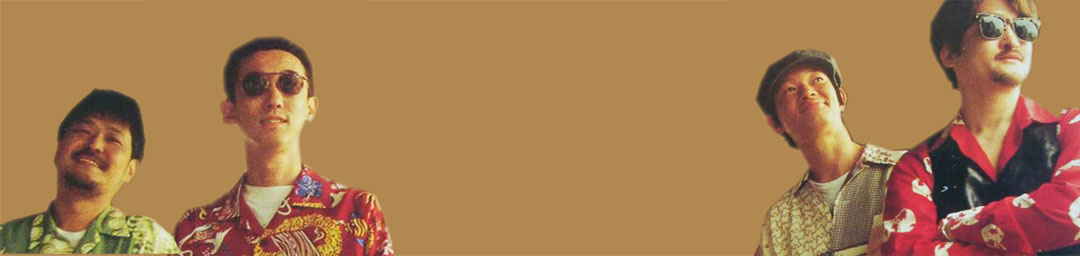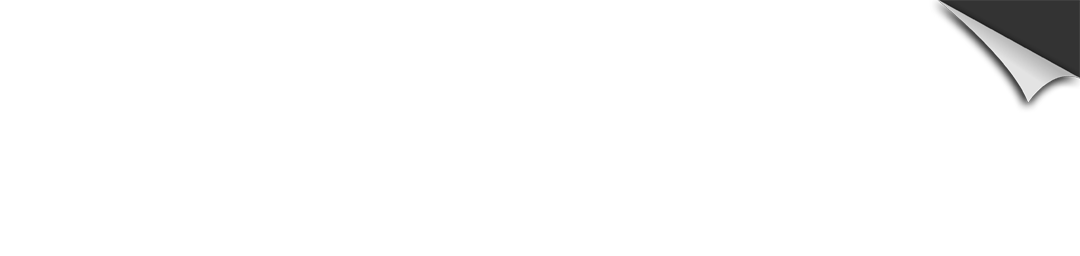ここから、いきなり私事になります。
この頃アタシは音楽をやっておりました。
正直「やってました」って胸を張れるほどちゃんとやってたわけじゃないんだけど、ユニットを組んで活動していたことは事実です。
アタシたちのユニットは目的というか目標がありました。ま、ユニットを組んで何かやるくらいだから目標があるのは当たり前かもしれないけど、そんな生易しいもんじゃない。というかこのユニットはけして一蓮托生のようなものではなかったんです。
ジャンルでいえば、一応はレゲエということになるのですが、それは最大公約数みたいなもので、みな、自分のやりたい音楽が違った。よく「音楽性の違いで解散する」なんてことがありますが、アタシたちのユニットは最初の、結成段階で違っていたんです。そしてそのことは各人がわかっていたことでした。
ならば何故ユニットを組んだのか?それはたったひとつだけ共通認識があったからに他なりません。
具体的に言えば「本当にやりたいことは売れなければ出来ない」という。
当時のレゲエ界隈は「音楽だけでメシを食ってる」人はほんのひと握りで、噂ではランキンタクシーと浪花男(なにわまん)だけと言われていました。ちなみにその後というかそれから数年後にMINMIや三木道三が売れましたが、アタシたちがやってた頃はその程度だったんです。
正直、誰も「売れて大金持ちになりたい、人気者になりたい」とは思ってなかったと思う。ただ、売れる状況にしなければ、つまり音楽でメシを食える状態まで持っていかなければ早晩音楽を辞めなければいけなくなる。それは避けたい、という思いだったんです。
もちろんレゲエというベースを崩してまで売れたいとは思ってなかったけど、それでも売れ線の楽曲をずいぶん研究した。この頃は小室哲哉の天下だったので、何故あそこまで売れるのか、ずいぶん研究したことを憶えています。
そんな折、アタシたちユニットにマネージャーがつくことになった。まだデビューも決まってないのにマネージャーとは尚早すぎる、と思われるかもしれませんが、ユニットのひとりがこの人と知り合いで、マネージャーとしてはなかば引退状態だった人に無理をいってやってもらう形になったのです。
つまりこの人、ド素人じゃない。このちょっと前まではバリバリのマネージメント業務をやってた人なんだから、ド素人に毛がはえた状態のアタシたちには不足はありません。
んで、アタシたちのマネージメントを引き受けるまで、若干の空白期間はあるとはいえ、直前まで誰のマネージメントをやっていたのかというと、何と憂歌団だという。
憂歌団のマネージャーが自分たちのマネージャーになる!これにはアタシも興奮を隠しきれませんでした。
もうこの頃には憂歌団はほとんど聴いてなかったとはいえ、彼らのズバ抜けた能力と音楽性の高さは嫌ってほどわかってたし、そんな彼らを見てきた人ならきっとアタシたちのユニットを引っ張り上げてくれるのではないか、という期待が膨らんだのです。
先に私事の結論から書いておきますが、些細なことから結局ユニットは自然消滅になってしまい、アタシの「音楽でメシを食う」という夢は儚く潰え去ったのですが、まァそれはどうでもいい。本エントリの趣旨と関係ないしね。
それより憂歌団の話です。
その憂歌団の元マネージャーからいろんな話を聞いた。アタシは暴露的なことつもりは一切ないのであくまで彼らの活動の話に絞りますが、この元マネージャーは「何とか憂歌団をメジャー路線に乗せたい」と考えていたというのです。
この件にたいして、憂歌団のメンバーはかなり強硬に反対したらしい。メジャーな存在になったら自分たちの色が薄れてしまう、と。
それでも元マネージャーも引かない。こんな実力のあるバンドを世間の人たちが知らないのはあまりにももったいない。せめて憂歌団の存在をそこまで音楽が詳しくない人にまで周知できないか?と。
「胸が痛い」を何度もアレンジを変えながらリリースしたり、「ゲゲゲの鬼太郎」の主題歌を歌ったりしたのはこのマネージャーの策略でした。策略って書いたら悪いイメージになるけど、ま、戦略でよかったな。
何とか話題作りだけはしよう。そのためには子供向けアニメの主題歌も歌わせる、という。
たしかにこの頃の憂歌団の楽曲(というかシングルリリースしたもの)は、良く言えばとっつきやすい、悪く言えば憂歌団らしさが希薄で、こんなことを言うとアレだけど、別に憂歌団がやらなくてもよいような楽曲ばかりです。
そんなことは百も承知で、とにかく世間的な代表曲があれば、ステージは今まで通りでもパイが膨らむ=もっと長期的に活動出来るという発想で動いていたわけで。
憂歌団には代表曲はありません。そりゃファンは「嫌んなった」とか「シカゴバウンド」とか言うのだろうけど、世間の人は知らない。かろうじて「おそうじオバチャン」がほんの少し知名度があるくらいで、それもまったくたいしたものではない。
代表曲=代名詞なわけですから、憂歌団と言えばコレという楽曲がない限り、世間的な知名度は上がらない。
それがいいことか悪いことかは問いません。ただかつてアタシたちがやっていたユニットが標榜した「本当にやりたいことは売れなければ出来ない」のも間違いないと思う。
そんなことを言えば「すでに憂歌団はやりたいことをやってたじゃねーか」と言われるかもしれませんが、将来にわたって、極端に言えば死ぬまでその地位を絶対的にするために「代表曲があるに越したことはない」という発想が間違ってるとは言えないと思うんです。
憂歌団はオリジナル楽曲だけでなくカバーもずいぶんしている。Page1で挙げた「JELLY ROLL BAKER S BLUES」もそうだし「嘘は罪」も古いジャズナンバーです。
歌謡曲のたぐいもずいぶんカバーしており、加山雄三の「君といつまでも」や藤圭子の「女町エレジー」(憂歌団は「イコマ」というタイトルを自称していた)もよく歌っていた。
 だから、というわけでもないんだろうけど、1994年に「知ってるかい?」というカバーアルバムをリリースしています。
だから、というわけでもないんだろうけど、1994年に「知ってるかい?」というカバーアルバムをリリースしています。
アタシはこれを聴いてなかったんだけど、近年聴いてみたら想像以上にダメだった。「刺身のツマとしてのカバー」ではなく「カバーが刺身」ってのに無理があるんだけど、それを差し引いても、ついでにスタジオ録音盤というのを差し引いても、これは失敗と言わざるを得ない。とにかく憂歌団ほどの人たちが本当にこの程度で満足したのか、不思議に感じるほどの出来の悪さで、オリジナルでなくてもいいから、カバーでも良いから代表曲を、というのも無理だった、としか言いようがない。
元マネージャーが辞めたこともあって、結局憂歌団のメジャー路線計画は道半ばで頓挫します。
そしてこの頃からヴォーカルの木村と他のメンバーの関係が悪くなった。
アタシはメンバー内のいざこざにはまったく興味がありません。そりゃあ個性の強い人たちだから何度も内輪揉めはあったんだろうけど、それでもバンドとして一流なのだからただのファンは文句を言う筋合いはない。
ただ解散となると話は別です。
たしかにこの頃のアタシは、再び憂歌団への関心はなくなってはいた。でも解散してしまうともう二度と彼らのライブが観れない。「メディア化されたものを聴いても何の意味もない、ライブこそが彼らのすべて」と考えるアタシのような人間にとって憂歌団の解散は、彼らへの関心が永久に失われたに等しかったわけで。
ちょっと時期ははっきりしないんだけど、たしか2000年代の後半、NHKのBSでやっていた音楽フェスのような番組を見てると木村がソロで何か歌っていたんです。
正直、これを見て愕然となった。これはアタシが知ってる木村の<声>ではない・・・。とにかく、何でこんなふうになっちゃったんだ、と強い憤りが去来したというか。
 木村はソロ活動をやる傍ら、近藤房之助と「クレイジードッグス」なるユニットを結成し、アタシが敬愛するクレージーキャッツの隠れた名曲「悲しきわがこころ」と「ショボクレ人生」をカバーしていました。
木村はソロ活動をやる傍ら、近藤房之助と「クレイジードッグス」なるユニットを結成し、アタシが敬愛するクレージーキャッツの隠れた名曲「悲しきわがこころ」と「ショボクレ人生」をカバーしていました。
さすがにこれは聴かないわけにはいかない、と思いCDを取り寄せたのですが、案の定、木村はかつての木村じゃなかった。とにかく声が出ていない。「天使のダミ声」と言われた面影が消えている。もし仮に、憂歌団が再結成したとしても木村がこんな状態ではどうしようもない、と。
しかも2012年になって長年ドラムをつとめてきた島田和夫の死が報じられた。(のちに自殺と発表)
憂歌団の場合、誰かが抜けた、誰かが死んだ、ならば代わりの誰かを、というわけにはいかないのです。そこが他のバンドと根本的に異なる。
能力云々は関係ない。いくら実力があろうとも、あの観客と対等になってグチャグチャにスクイーズする<感覚>がなければ代役なんてつとまるわけがないのです。
もうこれで、あの、アタシの音楽感を根本から覆した憂歌団はなくなった。たしかに島田和夫逝去後に再結成を果たし今も活動はしていますが、もうあの憂歌団ではない。しかも木村があの状態です。一時期よりは改善された気はするけど、年齢もあって完全に元に戻ったわけではない。
それでも逆に言えば、今の人たちがいくら観たくても観れない彼らの真髄をアタシは観た、とも言える。もう二度と観れないのはたしかだけど、そういう意味では非常にラッキーだったな、と思う自分もいるわけでして。
憂歌団には追体験は存在しない。仮に自分が行ったライブの音源がメディア化されたとしても、それは追体験とは言えない。当然、スタジオ録音されたものをいくら聴いても体験どころか聴いたうちにも入らないとさえ思う。
そこまで極端に、ある意味本来の意味での<藝人>だった彼らはアタシの中で永遠のものになった。もう、誰にも邪魔されない、アタシだけのものに。
そんな憂歌団に花束を贈るのは、もしかしたら違うのかもしれない。自分の心の内に花束を贈るようなものだから。でも、だからこそ、そんな刹那的なことをやってくれた今の憂歌団に花束を贈りたい気分なんです。
| 正直、もう20年以上前に友人の言った「憂歌団は好きだが憂歌団を語る人は好きではない」という言葉が頭から離れません。 やっぱり、そうなるのはその友人の言葉が理解出来るからで、何というか、憂歌団って触っちゃいけない人たちなんです。ましてや熱く語るなんてご法度の存在というか。 それがわかっていながらこんな文章を書いた。いやわかっているからこそ、憂歌団の音楽性への言及は極力避けて、あくまで「アタシと憂歌団の関係性」だけを書いたわけで。 |
|---|
@Classic #音楽 #体験 #1990年代 全2ページ 憂歌団 音楽活動 追体験 対等 PostScript #噂 #1970年代 #1980年代 #2000年代 #2010年代 #クルマ #物理メディア #雑誌 tumblr 画像アリ