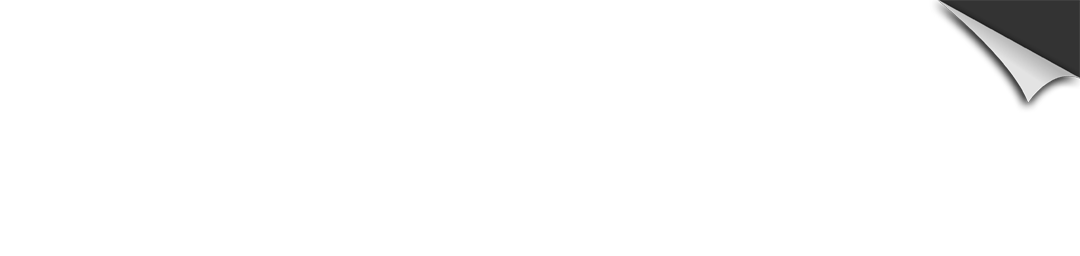手元に一冊の書籍があります。タイトルは「吉本興業百五年史」。ずいぶん分厚い本ですが、吉本興業の足跡を写真満載でまとめようとするなら、そりゃこの程度のページ数にはなります。
手元に一冊の書籍があります。タイトルは「吉本興業百五年史」。ずいぶん分厚い本ですが、吉本興業の足跡を写真満載でまとめようとするなら、そりゃこの程度のページ数にはなります。
と書けば察しがつくでしょうが、これは書籍というより<ほぼ社史>です。まァ社史は普通一般販売されませんが、これは一般販売されたものなので厳密には社史ではありません。でも内容的に<ほぼ社史>と見做しても問題ないはずです。
こういったものが一般販売されたのは、吉本興業をモデルにした朝ドラが制作されたからでしょう。でなければ105年なんて中途半端な時期に出すわけないし。
吉本興業の歴史を辿るのであれば明治時代から始めるのが筋です。「わろてんか」でしたか(アタシは見てない)、あの朝ドラでも物語のスタートは明治時代からだったはずです。
しかしさすがに、この駄文も明治時代から始める気はない。そんなことをしてたらいくら書いてもキリがありません。
ただしひとつだけ留意しておきたいのは、少なくとも大正期までの吉本はあくまで「寄席経営会社」だったということです。早い話が、今の人が吉本と聞いて連想する、いわゆる芸能プロダクションではなかったのです。
今の日本では芸能プロダクションが幅を利かせており、極端な話、いくつかの大手芸能プロダクションが芸能界を牛耳っている状態です。
しかし昭和のはじめまでは、なかなか芸能プロダクションという文化が根付かなかった。
さらに遡れば、興行の主体になっていたのは芸人たちであり、太夫元(興行主)が出演者を集めてプログラムを組むというやり方が行われるようになったのは大正に入ってからです。
(芸人、つまり出演者が主体となって興行を行う慣例は落語界でのみ続き、今でも当時のままではないものの近いことが行われている)
 日本で最初の本格的芸能プロダクションと言われるのは、渡辺晋が興した渡辺プロダクションです。これが1955年。つまり戦後10年も経った頃の話です。
日本で最初の本格的芸能プロダクションと言われるのは、渡辺晋が興した渡辺プロダクションです。これが1955年。つまり戦後10年も経った頃の話です。
ではそれ以前に芸能プロダクションがなかったのかというと、なくはなかった。しかしそれは今でいうプロモーターに近いもので、マネージャーのいる芸能人もいましたが、個人的に雇っているケースがほとんどでした。
マネージャーなんていうと、芸能プロダクションに雇われた、担当芸能人の売り込みからスケジュールまですべてを仕切るイメージですが、戦前の時点でこのような人はいない。まったくいなかったかと言われると不明な点もあるけど、たとえ大スターであっても興行会社及び映画会社との折衝は、大スター本人もしくは個人的に雇われたマネージャーがやっていたのです。
戦前のトップコメディアンだった古川ロッパの日記(「古川ロッパ昭和日記」)を読むと、ほぼ自身で細かい折衝までやっていることがわかります。
しかしそれではいろいろと不都合も出てくる。人気のあるスターには自分のところの興行なり映画に優先的に出て欲しい。出来れば同業他社には関わって欲しくない。商売であるのだからそれは当然です。
そこで「専属」という考え方が生まれた。専属契約を結べば同業他社の劇場や映画に出演出来ませんが、その代わりそれなりの額の専属契約料が支払われる、という仕組みです。
ただこれも、のちの芸能プロダクションとは考え方が違います。あくまで「専属契約」を結んだだけで、異業種の仕事の斡旋までしてくれるわけではない。
例えば東宝映画と専属契約を結んだとしましょう。この場合縛られるのは映画だけです。松竹や日活の映画には出られないけど、アトラクションであったり、ラジオに出たりは映画の撮影中でない限り、本人判断で自由に出来る。
けども、まあ当たり前だけど、東宝映画の職員がラジオ局に同行することはないし、ギャラの交渉なんかもしてくれないのです。
今の、つまりひとりのタレントの育成から売り出し、すべてのスケジュール管理までを一括で芸能プロダクションが面倒みる、というスタイルを作ったのは渡辺プロダクションでしょう。若干の先行例はあるとはいえ「タレントの作り方」みたいなマニュアル的なものを作ったのは間違いなく渡辺プロです。
それまで育成はタレント自身に任されていた。師弟関係を作り、弟子は師匠について芸を学ぶ。やがて幕間の<つなぎ>やチョイ役などで能力が認めれるようになれば、師匠のお墨付きが出てやっと興行会社や映画会社との専属契約が得られるという形でした。
つまり育成に芸能プロダクションが口出しする機会すらなかったのです。
これは吉本興業とて同じです。
 戦前の吉本はすでに能力があると認められた芸人や役者を専属という形で縛っただけで、のちのNSCのような養成学校がないのはもちろん、新人や売れてないタレントを使い物にする、というような<育成>をほとんどしてない。(ほぼ唯一の例外は安来節。林正之助はオーディションによって出雲の素人娘をスカウトし、一から徹底的にシゴキ上げたという。ま、モー娘。やAKB48がやったことの極めて初期の例と言えんこともない)
戦前の吉本はすでに能力があると認められた芸人や役者を専属という形で縛っただけで、のちのNSCのような養成学校がないのはもちろん、新人や売れてないタレントを使い物にする、というような<育成>をほとんどしてない。(ほぼ唯一の例外は安来節。林正之助はオーディションによって出雲の素人娘をスカウトし、一から徹底的にシゴキ上げたという。ま、モー娘。やAKB48がやったことの極めて初期の例と言えんこともない)
しかし<所属>ではなく<専属>なら、それも当然と言えるわけで、端から端まで面倒は見ないけど、すでに知名度を持ったタレントをより大きく羽ばたかせる=寄席経営の安定化を図る、というのは当時の常識からしたらまったく正しいやり方なのです。
このあたりについて「吉本百五年史」でも前田憲司氏はこのように書いています。
しかし、専属契約という概念は乏しく、月給制が導入されたといっても、決して社員のような扱いではなく、僅かな基本給をベースに寄席の出演回数を元にした出来高払いを加算したものであったようだ。
さて、黎明期の吉本興業を舞台にしたドラマ、と言えば2017年(~2018年)に「わろてんか」が放送されましたが、先ほど書いた通りアタシは見てない。
他には山崎豊子の作で、ドラマ化、映画化、舞台化された「花のれん」が有名ですが、アタシにとって黎明期の吉本興業のドラマ化と言えば1988年に「花王名人劇場」枠内で放送された「にっぽん笑売人」になってしまいます。
若き日の林正之助(当時の吉本興業社長)を演じたのは沢田研二ですが、現役吉本芸人が往年の名芸人を演じるのが<売り>で、エンタツ・アチャコ役をオール阪神・巨人が、ワカナ・一郎を宮川大助・花子が演じていました。
桂春團治を演じたのが横山やすしというのは当時なら妥当ですが、春團治(一般には<初代>と言われるが実は2代目にあたる。今ではこの春團治に敬意を表する意味もあって初代は<元祖>や<零代>と呼ばれている)はいわば吉本興業最初のスタータレントでした。だから「にっぽん笑売人」は春團治の登場からドラマがスタートしています。
しかし春團治は借金のカタに「止むを得ず」吉本興業と手を結んだと言われており、ただ吉本系の劇場に出演しただけとも言えます。
それを考慮すれば、吉本興業にとって本当の意味での最初のスタータレントは横山エンタツ・花菱アチャコであることは間違いありません。
エンタツ・アチャコと言えば近代漫才の祖として知られています。揃いの背広を着て舞台に上がり、歌も歌わず楽器も弾かず、ふたりの喋りだけで観客を笑わせる、というスタイルは画期的で、もちろん彼ら自身の才もあってあっという間に人気漫才師になりおおせたのです。
ここで留意が必要なのは、何故このようなシンプルかつスタイリッシュなスタイルの演芸が生まれたかです。
横山エンタツという人は出身こそ兵庫県の三田ですが、最初から大阪的な演芸をやろうとしていたわけではありませんでした。
昭和のはじめにアメリカを巡業したことが大きかったと言われていますが、彼が目指したのはチャップリンなどの欧米スタイルのコメディアン(喜劇人)で、ヴォードビリアン(演芸人)ではなかったのです。(チャップリンももとはパントマイム師=ヴォードビリアンでありますが)
成り行きで関西資本の吉本の専属になり、花菱アチャコとコンビを組むことにはなったのですが、旧来の演芸とは違うモダンな嗜好が最初からあったわけで、だから背広を着たスタイリッシュな、<万歳>ならぬ<漫才>というスタイルを生み出したのです。
エンタツ・アチャコのコンビ解散劇の話はオミットしますが、とにもかくにもふたりは映画や全国中継のラジオなどの限られた場所でのみコンビを続けていくことになります。
エンタツが目指していたのが欧米スタイルのコメディアンである以上、そして人気を引っ張っていたのがエンタツである、まして一度解散したコンビを再び組ませるわけですから、エンタツの意向が尊重されるのは当然で、そこで吉本は提携先であるP.C.L.と共同でエンタツ・アチャコ主演映画の製作にとりかかります。
もちろん製作された映画は大いにエンタツの意向が反映されたコメディで、たしかにアチャコとのコンビとして出演しているのですから、随所に漫才めいたふたりだけのやり取りが散りばめられているのですが、全体として見れば「エンタツを漫才師ではなくコメディアンとして見せる」ことを重要視した映画に仕上がっています。
P.C.L.という映画会社は音楽喜劇を得意とする、実にモダンな作風が売りの会社でした。
 エンタツ・アチャコ主演第1作「あきれた連中」は音楽劇でこそないものの、P.C.L.のカラーであるモダニズムが横溢した喜劇で、監督をつとめたのは岡田敬と伏水修。共同監督というのは今では珍しいのですが、当時はままあることでした。
エンタツ・アチャコ主演第1作「あきれた連中」は音楽劇でこそないものの、P.C.L.のカラーであるモダニズムが横溢した喜劇で、監督をつとめたのは岡田敬と伏水修。共同監督というのは今では珍しいのですが、当時はままあることでした。
岡田敬は喜劇を得意とする監督で、いや喜劇しか撮れない監督といった方がいいのかもしれない。戦後になって行方知らずになったため名が残りませんでしたが、笑わせるツボを心得た職人監督でした。
伏水修は黒澤明や本多猪四郎と同じく山本嘉次郎門下で、音楽に強く楽譜が読める能力があった。早逝したためこの人も名前が残らなかったわけですが、もし生きていれば数々の音楽劇(音楽喜劇)を生み出したことは間違いなく、黒澤明も山本嘉次郎の正統後継者として認めていたと言います。
脚本は永見隆二ですが、原作はエンタツ・アチャコの座付作者の秋田実が手がけ、エンタツとアチャコのセリフは秋田実が書いたと言われています。
もっとも漫才の宿命で、撮影時はあまりのアドリブの多さに監督も辟易したらしい。ま、これはしょうがない。
「あきれた連中」でも第2作の「これは失禮」でもいいのですが、見ればわかる通りエンタツのセリフ回しは完全な関西弁ではなく標準語に近い。
それを言えばエンタツの芸風そのものが東京風で、言葉こそ関西弁らしきものですが、彼の芸を見ていると<関西の芸人>と決めつけるのにためらいを覚えるほどです。
おそらく、だからこそ、東京でも大阪と同じようにウケた。戦前の東京で大阪の演芸をそのまま持ってきてもいきなり受け入れられるのはやはり難しく、エンタツのスタイリッシュかつ「あまり大阪臭がキツくない」芸風があればこそ東京でもウケて、全国的な芸人になれたわけで。
さてアタシは「戦前までの吉本は現在のような芸能プロダクションではない」というようなことを書いてきました。寄席を安定経営するために芸人を大きくすることはあっても、マネジメントのすべてを請け負っていたわけではない、と。
しかしエンタツ・アチャコの映画出演は吉本が映画会社と提携したことで実現した。マネジメントまではいくかどうかはわからないけど、コーディネートまでしたことは確実です。つまりこれまでの説明だけでは矛盾が出てきます。
実は吉本の多角経営化は、エンタツ・アチャコ主演映画が封切られる数年前から進行されていたことでした。
吉本が<寄席経営会社>から一歩踏み出して<エンターテイメント事業会社>への転身を図り始めたのは1930年と言われています。
これは今も昔も同じですが、経営者は「新しい文明」への警戒心が異常なほど強いものです。
食い扶持を奪われたらかなわない、ということなんでしょうが、映画はテレビを、テレビはインターネットを「敵視しながらも小馬鹿にする」みたいなことを繰り返してきました。
これは戦前期においても同様で、<舞台>の人は新興メディアである活動写真(映画)やラジオを「敵視しながらも小馬鹿に」していたのです。
 吉本においては専属芸人にたいし「ラジオへの出演を禁じる」という通達を出していたらしい。曰く「ラジオで(つまりはタダで)<芸>が聴けるようになると誰も寄席に来なくなる」という理屈からです。
吉本においては専属芸人にたいし「ラジオへの出演を禁じる」という通達を出していたらしい。曰く「ラジオで(つまりはタダで)<芸>が聴けるようになると誰も寄席に来なくなる」という理屈からです。
この禁を破ったのが破天荒で知られた桂春團治で、吉本サイドは最初激怒したらしいですが、何とラジオを聴いた人々が大挙、寄席へ押し寄せる事態になった。
 ラジオは寄席へ人を招く宣伝になる、と気づいた吉本幹部は方針を180度転換し、ラジオ局(当時はNHKしかないし、NHKという名称すらなかった)と提携することになります。
ラジオは寄席へ人を招く宣伝になる、と気づいた吉本幹部は方針を180度転換し、ラジオ局(当時はNHKしかないし、NHKという名称すらなかった)と提携することになります。
いわば偶然の産物でニューメディアへの接近をはかることになったわけで。
1932年には吉本興行部は吉本興業になりますが、見ればお分かりの通り「行」が「業」に変わっています。
興行というのは英語で言えば「ショー」であり、吉本の実態に則した名前です。しかし「興業(事業を興す)」ではまるで意味が違う。
ここらへんの経緯については「吉本興業百五年史」にも書かれてないので推測になってしまうのですが、どうもこの時期の前後に寄席を仕切るだけの単なるイベント会社ではなく、吉本というブランドを育てて日本を代表するようなエンターテイメント会社を標榜し出したのではないかと思うわけで。
事実、この頃から提携先が増えていき、映画で言えば最初は日活と提携、その後日活のトーキー部門を担う予定だったP.C.L.と提携し、さらにP.C.L.が東宝と急接近したことによって東宝との提携も始めます。
吉本が最初に東京に進出したのは大正期ですが、この時は寄席を経営していただけです。しかし1932年頃から本格的に東京への進出をはかり、吉本せい、林正之助の実弟である林弘高が東京の吉本を仕切ることになります。
林弘高は東京での地盤を作るため、徹底した東京ナイズドした方針をとっていきます。それまでの大阪的スタイルである土着的なものではなく、より東京的にハイカラでモダンにする、といった戦略です。
この「吉本モダニズム」は当時としては最先端で、同じく洒脱さを売りにしていた東宝と比しても引けを取らなかったと言われています。
戦前モダニズムに興味のない方には馴染みがない名前を出しますが、戦前のトップダンサーだった中川三郎を引き抜き、P.C.L.管弦楽団にいた谷口又士をスカウトして「和製スパイクジョーンズ(アメリカのコミックバンド。のちのフランキー堺とシティスリッカーズやクレージーキャッツに多大な影響を与えた)」を標榜したバンドを作らせるなど、あくまでアメリカナイズドされたモダンなステージにこだわったのです。
そして1934年、吉本モダニズムの頂点というべき興行が行われることになるのですが、ここでPage2に続く