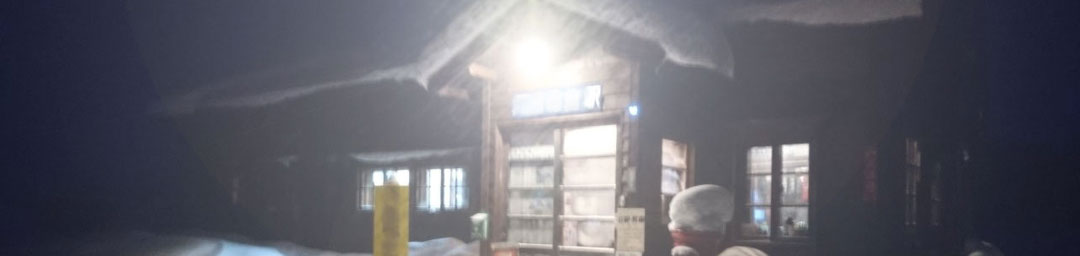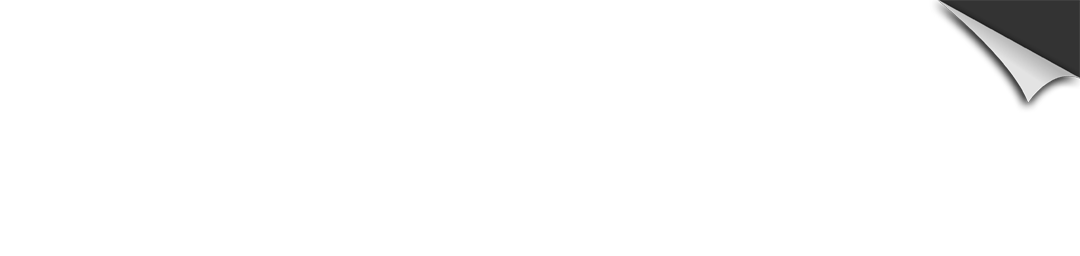大幅にブラッシュアップしたエントリをココに置いてます。
演歌はマイナーなジャンルとして落ち着いた、と言われてから久しいわけですが、当然、かつてはそうではなかった、という意味が含まれている。
ではそれがいつ頃の話なのか、とか、何故そういうことになったのか、というような文章を、少なくともアタシは読んだことがありません。
というわけで、これから演歌というものについて精査していきたいのですが、何も調べていない時点でも、これからどういうことをはっきりさせなきゃいけないかはわかります。
1. 演歌の興り
2. 演歌がメジャーになったタイミング
3. 演歌がメジャーだった時期
4. 演歌が衰退するきっかけ
5. 演歌が衰退した具体的な時期
これらの調査はさほど難しいものではありません。ちゃんとしたデータを当たれば具体的な<年>はわかります。
ただし<1>、つまり「演歌の興り」にかんしてだけは多少の知識が必要になる。というか「そもそも<演歌>とは何なのか」がわかってないことには不可能ということになるわけでして。
なので、読んでいただける方からすれば非常にかったるい話かもしれませんが、そこからスタートしなければならない。ま、少々、お付き合い願えれば、と思う次第です。
まず<演歌>というものの言葉の興りから書いていきます。
詳細はココを参照していただきたいのですが、演歌の<演>はもともと演説の<演>でした。つまりは演説歌をつづめての<演歌>だったのです。
しかしこの「演説歌=演歌」は現今の演歌とは似ても似つかないモノです。
明治時代から昭和初期にかけて作られた演説歌は、いわば社会風刺をするためのもので、正論を刺々しく声高に叫んでも誰も聞いてくれない。ならば<ユーモラスな歌>という形で、その中に社会風刺を盛り込む、というスタイルで世の中に受け入れられたのです。
つまり<演説歌>は後のコミックソングの原型になった、と言えるわけでして、現今演歌と呼ばれるものとは何の関係もない。
にもかかわらず名前だけが受け継がれたので混乱が生じてしまったというか。
では戦前期において<後の演歌の原型>がなかったのかというと、そういうわけではない。
一応、演歌の興りというか演歌第一号と言われているのは1931年にリリースされた「酒は涙か溜息か」と言われています。
しかしこれはいろいろな説があり、例えば大瀧詠一によると、これは演歌ではない、という判断ですし、それでもメロディラインを見るに演歌っぽくもある。
 何故このように意見が分かれるかというと、藤山一郎の歌唱に原因があります。
何故このように意見が分かれるかというと、藤山一郎の歌唱に原因があります。
藤山一郎はこの歌を歌うにあたって本邦初と言われる「クルーナー唱法」を取り入れた。クルーナー唱法とは「ささやくように歌う」のが特徴で、マイクロフォンの発達があって誕生した唱法です。
クルーナー唱法と言えばビング・クロスビーですが、どちらかといえば、いやどちらかといわなくてもジャズを歌うのに向いた唱法であり、「コブシを回して歌う」だったり「情念を込めて歌う」後の演歌の特徴とは真逆の歌い方である、と言えるのです。
だからか、「酒は涙か溜息か」を聴くと、演歌のようで演歌ではない、「民謡を今風(もちろんリリースされた1930年代)にアレンジしたもの」という感じがする。
 この楽曲の作曲者は演歌の礎を築いたと言われる古賀政男ですが、当時の古賀政男はまだ新進気鋭の存在であり、七五調の歌詞を見て民謡から着想を得たようです。
この楽曲の作曲者は演歌の礎を築いたと言われる古賀政男ですが、当時の古賀政男はまだ新進気鋭の存在であり、七五調の歌詞を見て民謡から着想を得たようです。
古賀政男と言えばあまりにも演歌のイメージが強すぎるのですが、クラシック畑の人であり、当時流行だったスイングジャズやブルースもずいぶん作っていたりします。
この時代(1930年代)を代表するもうひとりの作曲家といえば服部良一です。
 服部良一も実に様々なジャンルの音楽を手掛けているのですが、古賀政男とは真逆で「日本流ポピュラー音楽の礎」というイメージになっている。
服部良一も実に様々なジャンルの音楽を手掛けているのですが、古賀政男とは真逆で「日本流ポピュラー音楽の礎」というイメージになっている。
では服部良一は演歌っぽいものは手がけなかったのか、というと、実はあまり、そこには手を出していないのです。
ただし、淡谷のり子に書いた「雨のブルース」や「別れのブルース」、「私のトランペット」あたりは今の人が聴くと、もしかしたら演歌に聴こえるのかもしれない。
実はここに鍵があると思っています。
個人的な意見を言わせてもらえば、現今の演歌と呼ばれるものは「民謡+ブルース」ではないかと思うのです。具体的には「ブルースに七五調の歌詞と民謡チックなアレンジを加えたもの」とでも言えばいいのか。いや、もっと厳密に言うなら「民謡+新内+ブルース」か。
 アタシはそこまで音楽に明るくないので詳細な分析は無理ですが、ブルースと演歌の共通点は多い。少なくともイメージというかムードは間違いなく似通ったところがある。
アタシはそこまで音楽に明るくないので詳細な分析は無理ですが、ブルースと演歌の共通点は多い。少なくともイメージというかムードは間違いなく似通ったところがある。
淡谷のり子は死ぬまで演歌嫌いで通しましたが、これは一種の近親憎悪に近く、自身の愛したブルースがそこまで世に受け入れられず、演歌なる(おそらく淡谷のり子の中では)<ブルースのパチモン>が広く受け入れられたことに忸怩たる思いがあったのでしょう。
ここで時代は一気に1960年代初頭に飛びます。
この間、演歌に大きな動きはない。
戦前期に流行した「あゝそれなのに」に代表される「ねえ小唄」、そして1950年頃にちょっとしたブームになった「お座敷ソング」などは日本的な香りが濃厚なのですが、やはり、根本的に演歌とは異なる。
もう「演説歌をつづめての演歌」も遠い過去になり、演歌という言葉自体が死後になりつつあったのです。
その代わり、と言っては変ですが、1950年代の半ば頃から、Wikipediaふうに言えば「田舎調」、アタシ的に言えば「望郷ソング」のようなジャンルが生まれた。
 戦後、地方から東京に出てきて働き口を求める若者は急増しており、そうした人をターゲットにした、故郷を懐かしむような楽曲が次々と生まれます。
戦後、地方から東京に出てきて働き口を求める若者は急増しており、そうした人をターゲットにした、故郷を懐かしむような楽曲が次々と生まれます。
とくに三橋美智也の登場で、1950年代後半から1960年代前半(つまり昭和30年代)は望郷ソングの全盛期になった。その映画版とも言える吉永小百合主演の日活青春モノも多く作られた。
しかし「望郷ソング」はあくまで望郷ソングであって演歌ではない。民謡調のものが多いのだけど、先ほどアタシが定義した「民謡+新内+ブルース」からは外れています。
ただこれで潜在的な「時代から(もっといえば高度経済成長から)取り残された人、ついていけない人、違和感を持つ人をターゲットにする」という考えが生まれた、といっていい。
おそらくそうした人をターゲットにして、望郷の要素はあまりないんだけど「置き去りにされた<心>」をテーマにした、ある意味戦前の「別れのブルース」や「酒は涙か溜息か」をリバイバルしたような楽曲が作られだします。
 とくに1966年、美空ひばりによって歌われた「悲しい酒」は「酒は涙か溜息か」のオマージュといってよく、作曲も同じ古賀政男が手掛けている。
とくに1966年、美空ひばりによって歌われた「悲しい酒」は「酒は涙か溜息か」のオマージュといってよく、作曲も同じ古賀政男が手掛けている。
Wikipediaによれば、これは1960年に別の歌手によって歌われたカバーだったらしい。しかし、こうしてみれば1960年では若干早い、そして1966年というのは機が熟しており、大スターだった美空ひばりが歌ったことで、見事に起点となった、という感じですか。
それでも、アタシ的に言えば「悲しい酒」は演歌に限りなく近いが演歌ではない、というふうに聴こえます。
事実、この時期、つまりは1960年代後半に入った頃は、まだ「演歌歌手」というものは登場していない。後に演歌の大御所となる北島三郎は1960年代前半デビューですが、演歌、というよりは前時代の「望郷ソング」歌手といった色合いが強い。いや、後年になるにしたがって演歌的なアレンジが多くなっただけで、北島三郎はずっと「望郷ソング歌手」を通した人だったとも言えるんです。
ここにもうひとつ、1960年代後半からレコード業界を席巻した「ムード歌謡」の話をします。
アタシはムード歌謡の登場には必然を感じてしまう。と、その前に、急に話は変わりますが小室哲哉の話になります。
小室哲哉がユーロビートを基調にした、いわゆるJ-POPを作ろうとしたきっかけとして「ディスコかなんかに行って、その後カラオケに流れても、そういう場で歌う歌が当時はなかった」というようなことを語っていました。
マーケットを読み切った見事な判断ですが、これはムード歌謡にも似たようなことが言えます。
1960年代に入って、居酒屋でもなく、ダンスホールやサパークラブのようなところでもない、キャバレーと呼ばれる「夜の憩い場」とも言える業態が都会で急増していました。
当時のキャバレーにはたいてい専属のバンドがおり、ステージで演奏していたのですが、演奏するに向く楽曲があまりなかったのです。
何しろ<夜の憩い場>なのだから健全ムードの曲は合わないし、かといって客は音楽を聴きにきているわけではないのでジャンルとして尖った(当時で言えばモダンジャズやロカビリー)ものは必要ない。
一般大衆、誰が聴いても不快ではない、客の会話の邪魔にならず、それでいて<夜>にピッタリでムードが出るもの。それがムード歌謡です。
おそらくムード歌謡の原点は石原裕次郎の楽曲だったと思う。
 石原裕次郎が映画の劇中で歌うために作られた楽曲の大半はこれらの条件を満たしており、やがて石原裕次郎関係なく、映画関係なく、ムード歌謡としか言いようがない楽曲が多く作られるようなったんです。
石原裕次郎が映画の劇中で歌うために作られた楽曲の大半はこれらの条件を満たしており、やがて石原裕次郎関係なく、映画関係なく、ムード歌謡としか言いようがない楽曲が多く作られるようなったんです。
これまた後に演歌の大御所となる五木ひろしや森進一の初期の楽曲は完全にムード歌謡であり、いつの間にか両名をも含む大半の人が「演歌の人」扱いをされだしましたが、アタシは五木ひろしも、森進一も、完全にムード歌謡歌手だと思っている。
ムード歌謡は演歌とはまったく違います。まず民謡や新内といった日本調要素が限りなく薄い。また望郷ソングとも違っていて都会を舞台にしており、健全さもない。
<夜> <タバコ> <酒> <オンナ>
この4つはムード歌謡にとって非常に重要なキーワードで、そういうところからも現今の演歌との違いが見て取れます。
あ、えらく長々書いてますが、まだ「演歌の興り」の話です。つまり1960年代になってもまだ演歌はメインストリームにはなっていない。
「悲しい酒」以降、演歌という言葉が復活し、古賀政男調のもの=演歌調と言われるようにはなりましたが、実際、まだ「正真正銘の演歌」は生まれてはいない。
こうして見れば、演歌というのが如何に歴史の浅いジャンルかがわかるはずです。
演歌が本格化するのは甘めに見ても1970年代に入ってからであり、ジャンルとしての歴史はムード歌謡はもちろんグループサウンズやフォークソングよりも遅い。
「演歌は日本の心を歌ったもの」などという言葉を胡散臭く感じるのは、こうした歴史の浅さに起因するのですが、それはちょっと横に置いといて、話を続けます。
1970年代に入って、とんでもないことが起こります。
すでに演歌というものはあるにはあった。しかしその波はムード歌謡などと比べても小さいものでしかなかったのですが、ついに演歌というジャンルから特大ヒットが生まれるのです。
何がすごいといっても、演歌初の特大ヒット曲が「演歌のパロディ」だったことです。
音曲漫才トリオだったぴんからトリオが歌った「女のみち」がそれで、さらにコミックバンドだった殿さまキングスが歌った「なみだの操」が続いた。
さらにテレビドラマ「時間ですよ・昭和元年」の劇中で歌われた、さくらと一郎の「昭和枯れすゝき」も、やはり、演歌のパロディでこれまた大ヒットした。
ここに演歌というジャンルは確立した、と言っていい。
言っていいのですが、こうした過程を見ると如何に演歌の<興り>というよりは<成り立ち>ですが、が特殊なものだったのかがよくわるはずです。
演歌のもうひとつの特徴として「アレンジも、歌唱も、とにかくクドい」というのがありますが、演歌というジャンルが確立した<きっかけ>が芸人出身者によるパロディなんだから、それも当然と言える。パロディというからには如何に誇張するかが重要ですが、演歌の場合、その誇張したものがスタンダードになってしまった。そして誇張をスタンダード化することで世間に受け入れられたのです。
淡谷のり子の演歌嫌いの話は先述しましたが、こう考えるなら、嫌いで当然とも思えますね。
ここで一旦整理しておきます。
「民謡+新内+ブルース」を基本とした演歌は<誇張>を加えて正式にジャンルとして確立した。
確立した演歌というジャンルに、かつての望郷ソング歌手も、かつてのムード歌謡歌手もこぞって参戦し人材が一気に増え、演歌黄金期が始まるのです。
ここらでPage2に続く。