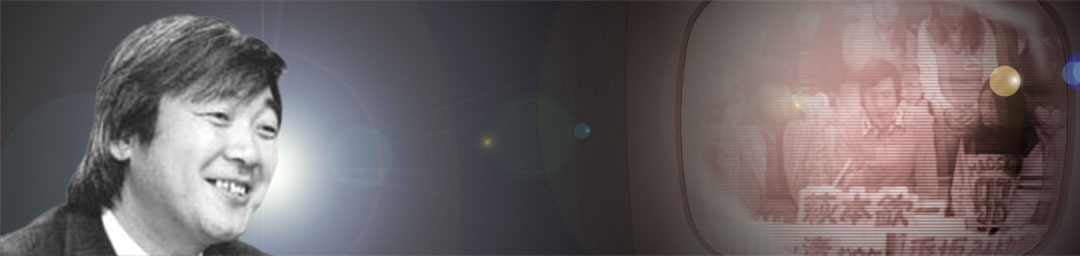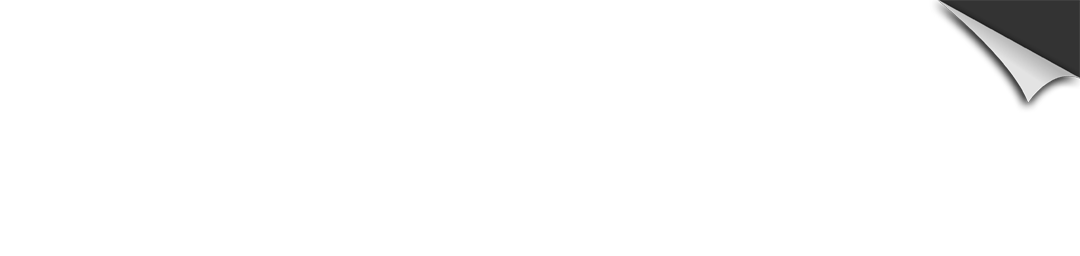さあてお立ち会い。これから笑いの話を始めるよ!
とまあ、出来る限りの軽さで始めてみたのですが、それに比べてエントリタイトルの仰々しいことよ。
ま、これには深ァ・・・そうで浅い理由があるわけでして。
1970年、言うまでもなく大阪万博が開催された年ですが、渡辺プロダクションの社長である渡辺晋はかねがね「万博で大スクリーンを使ったクレージーキャッツの映画をやりたい」との希望を持っており、1968年には山田洋次、鴨下信一、小林信彦らとブレーンストーミングまでおこなっています。
結果としては「笑い」をテーマにしたガスパビリオンのメイン上映作品としてクレージーキャッツ主演の短編映画が製作されました。
アタシはずっとこの映画のタイトルを「笑いの世界」だと思っていた。多数の資料にそうあったからです。
しかし「笑いの世界」というのはガスパビリオンのメインテーマとして使われた言葉で、映画そのもののタイトルは「笑いのシンフォニー」だった。これは万博の資料館みたいなところで確認したので、まず間違いないはずです。
とにかく映画のタイトルはわかったけど、今の時点でも詳しい内容はまだわかっていません。
2010年発行の「映画論叢」24号にて、「笑いのシンフォニー」の監督をつとめた木下亮がこの映画にかんしての手記を発表したり、また実際にこの映画を観た方から私信をいただいたりして、大まかな内容はわかったのですが、それでも極めて特殊な上映方法だったこともあり、おそらく二度と上映されることのない幻の作品になってしまったのです。
笑いというものはけして答えがあるものではありません。必勝法などは存在しない。つまり笑いについて書くなど雲をつかむような話なわけで、まァ幻を追う、という意味を込めて「笑いの世界」なんていう大仰なエントリタイトルにしたわけです。実際は「笑いのシンフォニー」だったけど、それは言いっこなしで。
さてさて、一応は大上段に振りかぶってみたのですから、まずは笑いの分類分けみたいなことからやりたいと思います。
ざっくり分けるならば
◇ ベーシックな笑い
これは基本の笑いと言い換えてもいい。
要は「人間は何故笑うのか」をすべて計算し尽くした形で笑わせるスタイルです。
このスタイルは演る側も観る側も、だから面白いんだ、と説明も納得も出来る。つまり分析が可能な笑いとも言えるわけで。
◇ 破壊の笑い
何というか、笑わせることよりも驚かせることに主眼を置いたスタイルで、極端な話、笑いよりもその場の空気だったり、観る側の安心感を破壊出来れば目的を達したと言えるスタイルを指します。
◇ 瞬間の笑い
人間というのはおかしなもので、あまりにも意外だったり、あまりにも<そのまんま>でも笑ったりするんですよ。
しかし基本、どちらも流れを無視したものであり、流れを無視し続けるということを実現させるためには中途半端なプロには無理なんですね。
まったくの素人の方が<意外>を導きやすいし、逆に十年一日同じことをやってるプロでないと<そのまんま>では笑いを取れない。
ある意味一番簡単で、一番難しいスタイルなんじゃないかと。
昔、萩本欽一という人がいました。いや今もご健在ですが、残念ながら今も第一線とは言い難い。だから過去形で書かせてもらいます。
 萩本欽一が世間に登場したのは「コント55号」というコンビのひとりとしてでした。いろいろな文献を読むと、彼らの登場による衝撃は生半可なものではなかったようです。
萩本欽一が世間に登場したのは「コント55号」というコンビのひとりとしてでした。いろいろな文献を読むと、彼らの登場による衝撃は生半可なものではなかったようです。
コント55号のコントは「ストリップ小屋の幕間のコント」そのままらしいですが、それまでテレビで流れていた、それこそ「シャボン玉ホリデー」などのコントをまさにぶっ潰さんといった勢いで、どこまでが役柄なのか、どこからが「素」なのかわからない、坂上二郎を萩本欽一が徹底的にコツき回すコントが大いなる衝撃を与えたことは容易に想像がつきます。
もし今の時代なら、コント55号は早々にネタを捨てて、司会や生ぬるいバラエティ番組に活路を見出そうとしたのでしょうが、まだそこまで時代が成熟しておらず、彼らは売れても売れてもテレビでネタをやり続けた。萩本欽一は新作至上主義だったそうだけど、そんなにポンポン面白いコントなんて出来るわけがない。<新作>と謳ってはみても、笑いの取り方など無数にあるわけではないので、どうしても前にやったのと似通ってくる。
結果、彼らはあっさり飽きられた。キツい言い方をすれば、同じようなコントを繰り返すことで大衆に見捨てられたのです。
この事は萩本欽一のトラウマになったと思う。もう一度、何とかして、大衆を振り向かせたい。しかしコントをやり続けるとまたぞろ飽きられる。
司会はやらない、と言い続けてきた萩本欽一は「スター誕生!」と「オールスター家族対抗歌合戦」の司会を引き受けたのですが、このことがターニングポイントになった。
素人にはコントのような予定調和は不可能であり、しかし予定調和が無理だからといって面白くないとは限らない。むしろ素人だからこそ可能な爆発力のある笑いがあるんだ、ということを学んだんです。
 これを極限まで突き詰めて、萩本欽一は数々のヒット番組を作ることになった。全主演番組の合計視聴率が100%を超えたことから「視聴率100%男」なんてことまで言われるようになったわけで。
これを極限まで突き詰めて、萩本欽一は数々のヒット番組を作ることになった。全主演番組の合計視聴率が100%を超えたことから「視聴率100%男」なんてことまで言われるようになったわけで。
この頃の萩本欽一の番組は異様に出演者が多いのですが、これは爆発力のある笑いが出来る人=半素人は爆発力はあるけど持続力がまったくない。だから物量作戦で次々と素人に毛が生えたレベルの芸人、もしくは芸人以外のタレント・歌手を投入するしかなかったからです。
長々と萩本欽一のことを書いたのは、彼の辿った道程に、その後の大半の芸人・コメディアンの動きがほぼ包括されているからなんですよ。
コント55号時代は、まァ言えば「破壊の笑い」の時代と言っていい。そして視聴率100%男時代は「瞬間の笑い」の時代です。今は今で「ベーシックな笑い」に力を注いでいる。一見見識なくコロコロとスタイルを変えているみたいだけど、よほど特殊な人以外は「これが一番スタンダードなやり方」なんです。
『人気が出て商売になっていけばいくほど、健全な人間になる。これはチャップリンの昔からの鉄則でしょ。世の中へ飛び出していく時は、目立つためにかなりハードなキャラで売り出していく。インパクト重視。』(「クレージー映画大全」田波靖男のインタビューより)
これは植木等について語ったものですが、『目立つために』既存の概念を破壊する存在として登場する、つまり「破壊の笑い」からスタートするのは必然なんです。
ところが世間から飽きられないようにするのは至難の業で、となると自分は扇の要にいて、周りを動かすしかない。
『萩本欽一は頭のいい男だと思う。(中略)自分は捕手になり、相手に極め球(ママ)を投げさせる。投手は次々に交代するが、自分は相変わらず捕手の座を守り得ている。』(色川武大著「なつかしい芸人たち『ロッパ・森繁・タモリ』」より)
自分が投手でさえなければ、自分が摩耗することはない。つまり飽きられることはないわけです。
しかし、これもやがて、本人がというよりは「やり方」が飽きられる。というか観る側に<手>を見透かされるようになる。
そして結局、最後には「確実に一定の笑いを得られ、磨耗することもなく、飽きられづらい」ベーシックな笑いへとたどり着く、と。
こうした典型的なパターンは、自分は芸人ではない、と常に意識していたタモリは別として、ほとんどの笑いを行う人に当てはまります。ダウンタウンでさえ、大局的に見れば当てはまっていると言えてしまう。
そんな中、例外と言えるのはビートたけしです。
 たしかにビートたけしは『ハードなキャラで売り出し』た。そこに違いはありません。
たしかにビートたけしは『ハードなキャラで売り出し』た。そこに違いはありません。
しかしたけしが他の人と決定的に違うのは、破壊のみが目的であり続けたことです。
もちろんたけしだって迷走した頃がある。たけし軍団なんて「捕手になろう」とした名残でしょう。
しかしこれ以降、たけしは一切ブレることがなかった。とにかく、ありとあらゆるものを破壊し続けたのです。
コントを壊し、バラエティ番組を壊した。そして「約束事」とか「予定調和」をすべて潰してしまったためテレビという枠さえ壊してしまったわけです。
挙句、テレビだけでは飽き足らず、とうとう映画の枠の破壊までし出した。こういったところはまさにビートたけしの面目躍如ですが、途中から「破壊ありき」になりすぎてしまったのではないか、とも思ってしまうんです。
たけしが予定調和を壊してしまったがために、予定調和内で笑いを作ろうとする人が出てこれなくなってしまった。そしてたけし以降「予定調和を壊す」という型が出来てしまって、結局似たようなタイプの人ばかりになってしまったってのもあると思う。
上岡龍太郎が「ブームになるほどの人が登場した後は必ず悪影響も残る」と言っていましたが、萩本欽一の後には「テレビにまともな芸など必要ない」という悪影響が残り、ビートたけしの後には「予定調和などをやるのは馬鹿だ」という悪影響が残った。
しかしこれはあきらかにテレビの寿命を縮めるやり方だった。いやそもそもテレビは笑いの発信源としてハナから向いてなかった、とかいろいろ言えるとはいえ、いわば天才の登場がテレビという新興メディアの寿命を短くしたってのは間違いないと思うわけで。
しかし、破壊の限りを尽くしたビートたけしでさえ、どうしても破壊出来なかった「笑いのスタイル」があります。
それが「フリートーク」なのですが、ここいらで次のページにバトンタッチします。